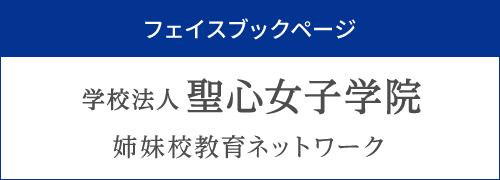ある先生が「枯葉にそっくりの虫がいます」と教えてくれました。確認してみたところクチバスズメというスズメガ科の蛾でした。枯葉に擬態している蛾です。そのことをお伝えすると「やっぱり枯葉ではなかったんですね」とおっしゃいました。それだけ蛾の擬態が見事だということです。

今日のことば
昨日の新聞から406 平成二十九年七月十七日(月)
『漱石辞典』(翰林書房)を読む
―― 一語を手掛かりに『坊っちゃん』を読みなおす ――
夏目漱石の生誕百五十年、没後百年を記念して翰林書房から『漱石辞典』が刊行されました。その辞典の中の「会津」と「午睡/昼寝」の項目を執筆したのが不二聖心の卒業生の伊藤節子さんです。今週は伊藤さんが執筆した「会津」の文章を手掛かりに、改めて『坊っちやん』という作品を読みなおしてみたいと思います。
『漱石辞典』では先ず「会津」に関連する『坊っちやん』の文章が引用されます。それらは次の箇所です。
◆帰りに山嵐は通町で氷水を一杯奢つた。学校で逢つた時はやに横風な失敬な奴だと思ったが、こんなに色々世話をしてくれる所を見ると、わるい男でもなささうだ。只おれと同じ様にせつかちで肝癪持ちらしい。あとで聞いたら此男が一番生徒に人望があるのださうだ。(「坊っちやん」二)
◆「君は一体どこの産だ」/「おれは江戸っ子だ」/「うん、江戸っ子か、道理で負け惜しみが強いと思つた」/「君はどこだ」/
「僕は会津だ」/「会津っぽか、強情な訳だ。今日の送別会へ行くのかい」(「坊っちやん」九)
以上が作品の引用で、これに伊藤節子さんの文章が続きます。
「坊っちゃん」における江戸讃美と田舎への排他意識は、坊っちやんの単一的性格を象徴して印象的である。しかし唯一朋友関係を結ぶ数学の堀田、通称山嵐は会津出身である。作品の勧善懲悪的世界から言えば、赤シャツ、野だを敵に、山嵐は坊っちやんの味方に位置するのであり、「会津っぽ」の「癇癪持ち」「強情張り」「頑固」さは短所というよりはむしろ、親しみとして描かれている。
ここに明治維新の背景を鑑みれば「これでも元は旗本だ。旗本の元は清和源氏で、多田の満仲の後裔だ」という旧幕臣出の坊っちやんと、旧幕府勢力である会津出身の山嵐とは平岡敏夫が「『坊っちやん』試論」(『文学』1971・1)で指摘するように佐幕派という同志で結びつくのである。
彼らは赤シャツと野だを懲らしめ満足げに「不浄の地」を去るが、その地の権力体制は変わらないであろう。山嵐への親近感は、会津へのそれとも重なって、一方に明治政府の権力構造を照らし出しもするのである。(伊藤節子)
『坊っちやん』の登場人物の中では、山嵐だけが坊っちゃんとうまが合い、二人で力を合わせて赤シャツらを懲らしめることはよく知られていますが、二人を結びつける要素として佐幕派という共通点があることは意識していませんでした。この視点を持つと物語は、それまでとは違った色合いをおびてきます。
そのことを確かめるために、二人が「赤シャツと野だを懲らしめ」て「不浄の地」を去る場面を引用しましょう。赤シャツと野だが芸者の待つ宿屋に入っていくのを見た坊っちゃんと山嵐は、二人が再び現れるのをじっと待ちます。
赤シャツの来るのを待ち受けたのはつらかったが、出て来るのをじっとして待ってるのはなおつらい。寝る訳には行かないし、始終障子の隙から睨めているのもつらいし、どうも、こうも心が落ちつかなくって、これほど難儀な思いをした事はいまだにない。いっその事角屋へ踏み込んで現場を取って抑えようと発議(ほつぎ)したが、山嵐は一言にして、おれの申し出を斥(しりぞ)けた。自分共が今時分飛び込んだって、乱暴者だと云って途中で遮られる。訳を話して面会を求めれば居ないと逃げるか別室へ案内をする。不用意のところへ踏み込めると仮定したところで何十とある座敷のどこに居るか分るものではない、退屈でも出るのを待つより外に策はないと云うから、ようやくの事でとうとう朝の五時まで我慢した。
角屋から出る二人の影を見るや否や、おれと山嵐はすぐあとを尾(つ)けた。一番汽車はまだないから、二人とも城下まであるかなければならない。温泉(ゆ)の町をはずれると一丁ばかりの杉並木があって左右は田圃になる。それを通りこすとここかしこに藁葺があって、畠の中を一筋に城下まで通る土手へ出る。町さえはずれれば、どこで追いついても構わないが、なるべくなら、人家のない、杉並木で捕まえてやろうと、見えがくれについて来た。町を外(はず)れると急に馳(か)け足の姿勢で、はやてのように後ろから、追いついた。何が来たかと驚ろいて振り向く奴を待てと云って肩に手をかけた。野だは狼狽の気味で逃げ出そうという景色だったから、おれが前へ廻って行手を塞いでしまった。
「教頭の職を持ってるものが何で角屋へ行って泊まった」と山嵐はすぐ詰(なじ)りかけた。
「教頭は角屋へ泊って悪いという規則がありますか」と赤シャツは依然として鄭寧(ていねい)な言葉を使ってる。顔の色は少々蒼い。
「取締上不都合だから、蕎麦屋や団子屋へさえはいってはいかんと、云うくらい謹直な人が、なぜ芸者といっしょに宿屋へとまり込んだ」野だは隙を見ては逃げ出そうとするからおれはすぐ前に立ち塞がって「べらんめえの坊っちゃんた何だ」と怒鳴り付けたら、「いえ君の事を云ったんじゃないんです、全くないんです」と鉄面皮に言訳がましい事をぬかした。おれはこの時気がついてみたら、両手で自分の袂を握ってる。追っかける時に袂の中の卵がぶらぶらして困るから、両手で握りながら来たのである。おれはいきなり袂へ手を入れて、玉子を二つ取り出して、やっと云いながら、野だの面へ擲(たた)きつけた。玉子がぐちゃりと割れて鼻の先から黄味がだらだら流れだした。野だはよっぽど仰天した者と見えて、わっと言いながら、尻持をついて、助けてくれと云った。おれは食うために玉子は買ったが、打(ぶ)つけるために袂へ入れてる訳ではない。ただ肝癪のあまりに、ついぶつけるともなしに打つけてしまったのだ。しかし野だが尻持を突いたところを見て始めて、おれの成功した事に気がついたから、こん畜生、こん畜生と云いながら残る六つを無茶苦茶に擲きつけたら、野だは顔中黄色になった。
おれが玉子をたたきつけているうち、山嵐と赤シャツはまだ談判最中である。
「芸者をつれて僕が宿屋へ泊ったと云う証拠がありますか」
「宵に貴様のなじみの芸者が角屋へはいったのを見て云う事だ。胡魔化せるものか」
「胡魔化す必要はない。僕は吉川君と二人で泊ったのである。芸者が宵にはいろうが、はいるまいが、僕の知った事ではない」
「だまれ」と山嵐は拳骨を食わした。赤シャツはよろよろしたが「これは乱暴だ、狼藉である。理非を弁じないで腕力に訴えるのは無法だ」
「無法でたくさんだ」とまたぽかりと撲なぐる。「貴様のような奸物はなぐらなくっちゃ、答えないんだ」とぽかぽかなぐる。おれも同時に野だを散々に擲き据えた。しまいには二人とも杉の根方にうずくまって動けないのか、眼がちらちらするのか逃げようともしない。
「もうたくさんか、たくさんでなけりゃ、まだ撲ってやる」とぽかんぽかんと両人(ふたり)でなぐったら「もうたくさんだ」と云った。野だに「貴様もたくさんか」と聞いたら「無論たくさんだ」と答えた。
「貴様等は奸物だから、こうやって天誅を加えるんだ。これに懲りて以来つつしむがいい。いくら言葉巧みに弁解が立っても正義は許さんぞ」と山嵐が云ったら両人共だまっていた。ことによると口をきくのが退儀なのかも知れない。
「おれは逃げも隠れもせん。今夜五時までは浜の港屋に居る。用があるなら巡査なりなんなり、よこせ」と山嵐が云うから、おれも「おれも逃げも隠れもしないぞ。堀田と同じ所に待ってるから警察へ訴えたければ、勝手に訴えろ」と云って、二人してすたすたあるき出した。
おれが下宿へ帰ったのは七時少し前である。部屋へはいるとすぐ荷作りを始めたら、婆さんが驚いて、どうおしるのぞなもしと聞いた。お婆さん、東京へ行って奥さんを連れてくるんだと答えて勘定を済まして、すぐ汽車へ乗って浜へ来て港屋へ着くと、山嵐は二階で寝ていた。おれは早速辞表を書こうと思ったが、何と書いていいか分らないから、私儀(わたくしぎ)都合有之辞職の上東京へ帰り申候につき左様御承知被下度候(さようごしょうちくだされたくそろ)以上とかいて校長宛てにして郵便で出した。
船は夜六時の出帆(しゅっぱん)である。山嵐もおれも疲れて、ぐうぐう寝込んで眼が覚めたら、午後二時であった。下女に巡査は来ないかと聞いたら参りませんと答えた。「赤シャツも野だも訴えなかったなあ」と二人は大きに笑った。
その夜おれと山嵐はこの不浄な地を離れた。船が岸を去れば去るほどいい心持ちがした。神戸から東京までは直行で新橋へ着いた時は、ようやく娑婆へ出たような気がした。山嵐とはすぐ分れたぎり今日まで逢う機会がない。
清の事を話すのを忘れていた。――おれが東京へ着いて下宿へも行かず、革鞄(かばん)を提げたまま、清や帰ったよと飛び込んだら、あら坊っちゃん、よくまあ、早く帰って来て下さったと涙をぽたぽたと落した。おれもあまり嬉しかったから、もう田舎へは行かない、東京で清とうちを持つんだと云った。
その後ある人の周旋で街鉄の技手になった。月給は二十五円で、家賃は六円だ。清は玄関付きの家でなくっても至極満足の様子であったが気の毒な事に今年の二月肺炎に罹かって死んでしまった。死ぬ前日おれを呼んで坊っちゃん後生だから清が死んだら、坊っちゃんのお寺へ埋めて下さい。お墓のなかで坊っちゃんの来るのを楽しみに待っておりますと云った。だから清の墓は小日向(こびなた)の養源寺にある。
伊藤さんの文章を読んだあとで、以上の箇所を読むと、権力者たちに最後の抵抗を試みる佐幕派の子孫たちの姿は、物語の筋とは別に、明治維新の時代に新しい権力者に対して抵抗を続けた幕府側の人々の姿を思い出させます。幕臣の子孫であることを自覚する坊っちゃんと会津人の特徴を身に備えた山嵐は、赤シャツへの懲らしめには成功しますが、結局は変わらぬ権力構造を残したまま、愛媛の松山の地を去ります。そして物語はあの有名な、清のその後を語る最後の場面(『坊っちゃん』を三十四回読んだという作家の井上ひさしは、作品の最後の一文を希代の名文と讃えました。)に移って終わります。今まではその場面をとてもせつなく、味わい深い場面だと思ってきましたが、今回は、「その後ある人の周旋で街鉄(現在の都電の前身)の技手になった」という一節が、別のせつなさを感じさせる、味わい深い箇所として心に残りました。佐幕派の子孫の坊っちゃんは、佐幕派に敵対する勢力が推し進めた近代化を象徴する鉄道の仕事につき、その後の人生を送りました。近代社会のシステムの中に組み込まれて鉄道技師として黙々と働き続け、坊っちゃんはその生涯を終えたことでしょう。「会津」という、『坊っちやん』を読み解くキーワードを知ったことで、名作『坊っちゃん』は過ぎ去った時代に対する挽歌のような作品に思えてきました。
伊藤節子さんがお書きになった、もう一つの項目「午睡/昼寝」は、漱石の文学の大切な要素として、「反近代の文学」という側面を忘れてはならないことを教えてくれます。不二聖心の図書館には伊藤さんから寄贈された『漱石辞典』が入っています。ぜひこの辞典を手に取り、一語にこだわることで深まる文学の感動を味わってください。