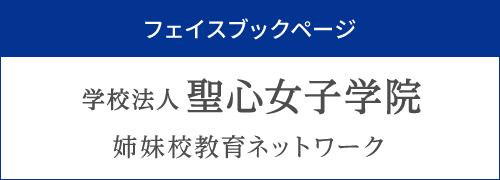フィールド日記

2013.04.04
貝母(バイモ)の花
2013.04.04 Wednesday
中里恒子に「貝母(バイモ)の花」という小説があります。約50ページの短編ですが、バイモの花にふれた部分はわずか数行です。その部分を引用してみましょう。
せまい庭に、貝母の花がいちめんに咲きひろがつてゐる。点点と、花はうなだれて咲いていた。
「よくふえましたね、」
「これだけは、大事にして、前の家から移しました。花は、たつた五日か七日咲くために、一年中埋もれてね……」
風にゆれて、つぼんだ花芯がゆらゆらゆらめくのを、わたしは、無心に眺めてゐた。
短いですが、忘れがたい印象を残す一節です。
今の時期の不二聖心では、まさにこの小説の描写にある通りの、花芯のゆらめく姿を東名高速沿いの道で見ることができます。


今日のことば
昨日の新聞から211 平成22年10月25日(月)
『不器用な日々』(清水眞砂子 かもがわ出版)を読む
―― あなたの心に火を灯す一冊のエッセイ集 ――
金曜日に静岡市にある私学会館に出張しました。私学会館から静岡駅に向かう途中に谷島屋という、個性的な品揃えの書店があります。帰りに店の中を覗いて見て一冊の本が目にとまりました。児童文学者の清水眞砂子さんの『不器用な日々』というエッセイ集です。手にとってページをめくり、すぐにこの本を購入することを決めました。長い間、探し続けていたエッセイが収められていることを知ったからです。それは「あこがれを手放すとき」というエッセイで、4年前に『婦人之友』という雑誌で読んだときの感動が忘れられず、何とかしてもう一度読みたいと思い続けてきた文章でした。次のような内容のエッセイです。
個人的な体験から語ろうと思う。小学校3年か4年のある日、私は同じ集落の子どもたちと缶けりをしていた。Kさんが鬼になった(当時私たちは子ども同士さんづけで呼びあっていた)。Kさんはみんなより少し動作がのろかったから、なかなか鬼からはずれなかった。私はKさんをこのままいつまでも鬼にしておいてはいけないと思った。自分がグループのリーダーであることは自覚していたのだ。が、同時に、Kさんがぐずだからいけないんだ、と別の声がささやいた。缶けりはそのまま小一時間も続いただろうか。どのように終わったかは憶えていないが、とにかく終わって、子どもたちはばらばらに家路についた。
この日のことがやがて私を苦しめることになった。大学3年のときだったと思う。私は半年ほどまともに外を歩けなくなった。授業にはとりあえず出ていたが、うわの空だった。人ごみの中を歩いていると、もし今、鎌をこの手にしたら、自分はすぐ前をいく人の首を掻き切るかもしれないと思った。悪が瞬間、私を支配したら、何だってやりかねないと思った。私は身をひそめて、本ばかり読んでいた。自分を肯定できる何物も見つからなかった。幼い頃のことも次々とよみがえってきた。その中に缶けりをしたあの日の風景があった。何てひどいことを! なんという意地悪を! しかし、それが自分だった。醜い自分。人でなしの自分。私はきりきりと自分を責めた。
それから6、7年して、結婚し、人の子の母となったKさんが私の家に遊びにきてくれたとき、――Kさんは中学校を卒業して以来別の道を歩いていたのに、会うと気さくに声をかけてくれていたーー、私はあの缶けりのときの自分の非をわびた。Kさんは忘れているようだった。あるいは忘れたふりをしてくれたのだったか。
Kさんのことだけではない。大学生のあの頃、私は自分が家族を含め周囲の人たちにしてきた行為のひとつひとつを思い出し、こんな自分がこの世に生きていていいのだろうかと毎日自分を責め、自殺を考え続けた。が、自殺もできない自分がそこにいた。どうしたらいいか。私はこれまでの己の言動をわび、この世にいることを許してくださいと、見えないものに向かって、ひたすら頼むほかなかった。神がいてくれるなら神にと思ったが、そのときも、そして、今に至るまで、私は神に出会えていない。いじめたのはあの缶けりの日のKさんだけではない。同じ頃、私は時折妹に意地悪をした。幼いなりに、自分がなぜそうするのかはわかっていた。私は我慢していたのだ。家族の誰に言われたのでもないのに、我慢していた。家が苦しいのがよくわかっていた。私はごはんにかけるふりかけも始末しなくては、と自分に言い聞かせた。ところが三つ下の妹は好き放題にかけている。こちらはこんなに我慢しているのに。そんなとき、私はちくりちくりと妹をいじめた。このことでも、私はのちに自分を責めた。幼い妹に何がわかっていたというの。ただ食卓のものをたのしんでいただけなのに。
たかがわずかなふりかけのことで勝手に我慢し、我慢しない妹に意地悪したことを私は今もすまなかったと思っている。私は我慢して「いい子」「いい人」をやっている人が、そうしていない人をいじめたくなる気持ちがわかる。わかるが、それは何とも貧しい、情けない行為だ。(中略)
おまえのは小さないじめだと人は言うかもしれない。が、いじめに大きいも小さいもない。いじめは、いじめである。(中略)
今、小中学生の間で起こっていると報道されるいじめの話を聞くと、先にいじめに大きい小さいはないといったものの、私が体験したものとは質も規模も異なってきているように思われる。子どもの私はなぜ、あの時点で引き返せたのか。今もなお引き返すことのできる子どもはいるはずだし、そもそも、いじめに手を染めない子どもも大勢いるはずである。阪神大震災のあとは、しばらくいじめが起こらなかったとも聞く。それは何によってか。
二年ほど前、どうしたらいじめがなくなるか、と学生たちと話し合っていたとき、ひとりの学生がさらりと言ってのけた。「授業が面白かったら、いじめなんて起きませんよ」。ああ、本当だ、と私は思った。今思えば、あれはいじめだったのかもしれないと思うものにも、子どもの私はでくわしている。だが、私は自分を加害者として責めはしても、被害者と思ったことがない。私はいじめとは意識しないまま、つらいときは普段以上に勉強し、本を読んだ。そうやって自分を支えていた。自分の自尊心を支えていた。学生時代、自分を責めて責めて責め続けたのだって、自尊心あってのことだったかもしれない。人間として恥ずかしいとの思いがなければ、あれほど苦しむことはなかったに違いない。そして、そう、私には憧れがあった。子ども時代も今も。
学生が言うのは本当だ、と改めて思う。授業が面白かったらいじめなんて起こらない。ならば、その面白い授業とは?
それは、はるかなものへの憧れを私たちの中にはぐくんでくれる授業であり、己の内深くおりてゆけるはしごを差し出してくれる授業である。この学生と付き合っていると、それがよくわかる。彼女の視野にはいつもはるか遠くのものが入っている。小中学生には無理だなどとは決して言うまい。はるかなものとは、手の届かない遠いところにばかりあるとは限らない。神秘は日々のくらしの中にある。身近な草木や石が、雨や風が、色や形が、ことばや物語が、人々の生活技術が、私たちをはるかなものへと誘ってくれる。私たちに遠くを見せ、深みをのぞかせてくれる。学生が言うのは、日々の授業が、この世界の不思議への扉を開けてくれるものになっているならば、子どもたちは、くだらないいじめなどにうつつをぬかしているはずはない、ということだ。それなのに、今、子どもたちは傲慢にこそなれ、自尊心を奪われ、気がつけば「憧れ」はほとんど死語になっている。はるかなものへのまなざしなど、大人も子どもも、とうにどこかに置き忘れ、「ふつう生きる」などという、ありもしない幻想を追うことにやっきとなっている。よりよき人間に憧れ、そこに一歩でも近づこうとする真面目さも、私たちの先を生きた人々がずっと大切にしてきた自由への憧れも、さまざまな不思議に驚くことも、「ふつう」からはずれたものに見える。憧れを手放したとき、人は「ふつう」を標榜するようになるのだろうか。となれば「ふつう」はすさみであり、いじめの最大の温床になりうる。いや、すでになっていると人々は気づきながら、さらに「ふつう」を目指そうとしている。
成果主義も「ふつう」だと政府はさらに追い打ちをかけ、教育現場にさらに「ふつう」を持ち込もうとする。このままでは、いじめは増えこそすれ、減ることはないであろう。
このエッセイを読み、「はるかなものへのあこがれ」を生徒の心に育てる授業をしたいと強く思ったことを昨日のことのように記憶しています。その思いは、ぼくのなかにずっとあり続け、この年の終わりにその思いを詩にして曲をつけ、卒業式の日のホームルームで、生徒へのはなむけの言葉として歌ったことも覚えています。それは次のような歌詞でした。
はるかなものへの憧れを
はるかなものへの憧れを あなたは忘れないで 育ててください
どんなときも それはあなたの 希望になる
遠い国 遠い昔 はるかな未来 広い空
あなたはまだ人生を歩みはじめたばかり
はるかなものへの憧れを あなたは忘れないで 育ててください
どんなときも それはあなたの 希望になる
つらい時 楽しい日々 忘れられないあの思い出
すべての先に新しくきっと何かが生まれる
この曲を心に蘇らせつつ、「あこがれを手放すとき」を再読し、さらに他の文章も読んでいきました。その中で、とりわけ印象深かったのは、2010年1月29日に青山学院女子短期大学で行われた最終講義の内容でした。清水眞砂子さんは、学生たちに最後に一つのお願いをします。
今日は最後に、特に学生さんにお願いしたいことがあります。この人に出会えたから自暴自棄にならずにすんだと、そう思われるひとりにいつの日かなってほしい。この人に会ったから、この人に出会えたから生きられたという、そういうひとりになってほしいということです。何とか食べていければ、社会的地位などというものはどうでもいいものです。あなたがいてくれてよかった、おかげで人間なんて、どうせ、と言わずにすんだという、もっと言えば、子どもの本がしてきたような仕事、そういう子どもの本の一冊に、皆さんおひとりおひとりがなってくれたら、と願っています。
この一節を読んで、何かが自分の中で変わったと感じました。そして、「先生」について語った次の言葉を思い出しました。
普通の先生は、よくしゃべる。
よい先生は、何かを説明しようとする。
優秀な先生は、教えたことを自分自身が模範となって示す。
そして偉大な先生は、出会う人の心に火を灯す。
ぼくの中で何かが変わったと思った瞬間は、ぼくの心に一つの火が灯った瞬間だったのでしょう。清水眞砂子という児童文学者は一人の偉大な教師でもあったのだとこの本を読んで改めて思いました。