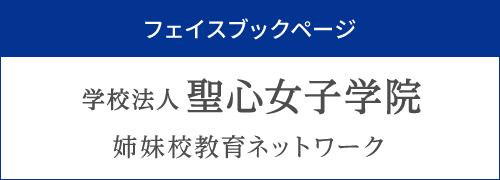フィールド日記

2013.03.13
ヤマガラの鳴き声の多様性
2013.03.13 Wednesday
北村薫に『盤上の敵』という素晴らしい作品があります。その最後のページに次のような一節があります。
わたしとあなたは、黒ずんだ土を踏み、そんな鬱蒼と茂る林の中を進んで行くのです。どこまで行っても、耳には追いかけるように渓流の音がついて来ます。水の響きを伴奏に、時々、高く澄んだ山雀(やまがら)の声が、ツツピー、ツツピーと聞こえて来ます。
この一節を読んでから、「ツツピー、ツツピー」というヤマガラの声を耳にするたびに『盤上の敵』という名作のことを思い出すようになりました。幸せなことに今の時期、不二聖心では毎日のようにこのヤマガラの声を耳にすることができます。
ヤマガラの鳴き声と言えば「ツツピー」だと思い込んでいたところ、この春、全く違ったヤマガラの声を聞くことができました。はじめは何の鳥かと思いましたが、専門家の方のご教示によってヤマガラの声であることがわかりました。どうぞ画像をクリックして、鳥の鳴き声の多様性を感じてみてください。
今日のことば
昨日の新聞から217 平成23年1月3日(月)
『盤上の敵』(北村薫 講談社文庫)を読む
―― 再生への祈りの物語 ――
冬休みに尊敬する作家・川上弘美の『大好きな本』(文春文庫)という書評集を読みました。その中に北村薫の『盤上の敵』というミステリーを評した次のような文章がありました。
個人的なことなのだが、ミステリーを読むのが怖い。なぜ怖いんですあんなに面白いものなのに、と問われれば、人が殺されるのが怖いのです、と、いつも答えている。
北村薫のミステリーでは人はめったに死にませんよ、とある時勧められて、読みはじめた。本格的な謎解きである。それなのに、本当にめったに人は死なない。日々の生にひそむ事件を、登場人物が理を以て解決してゆく。多く読むうちには殺人もあった。しかし怖さは感じなかった。なぜなんだろう。
つらつら考えながら最新作である本書を読み、驚いた。ミステリーの内容を明かしてはいけないからくわしく書かないが、北村作品には珍しく、深刻な殺人が据えられた物語なのである。それならばこの作品に限っては怖いのか。不思議なことだが、やはり怖くないのである。
「私は、推理小説に登場してくる探偵役を、決して好きではない。他人の秘事を、あれほどの執拗さであばきたてねばならないのか」
と言ったのは、司馬遼太郎である。なるほど、と思う。
つまるところ、わたしが怖いと感じるのは、本の中で起こる「事件と解決」そのものではない、のではないか。そうではなく、「事件と解決」という事象に対する、登場人物のあまりの迷いのなさ、それこそが「怖さ」の核なのではないか。
北村ミステリーの登場人物は、迷う。躊躇する。事件を解決しながらも、解決すること自体に、大いなるかなしみを感じている。そして今回の作品の中では、殺人というものを行う者もまた……。
怖くないミステリーなのだ。しかし、深い。深い湖のような、ミステリー。あっというどんでん返しのラストまで用意された本格ミステリー、その中でこれだけ人というものの不可思議さが描かれていることは、大いなる喜びであった。
比喩の力というのは恐ろしいものです。僕は「しかし、深い。深い湖のようなミステリー。」という表現に魅せられて、すぐに『盤上の敵』を購入しました。
読み始めて「あれ」と思いました。ミステリーには異例のことですが、作者の前書きが付いていたのです。次のような「前書き」です。
ここは購入する前に、読んでいただきたいのです。
『盤上の敵』は、まず、わたしを楽しませてくれた「ミステリのあるタイプ」に対しての御礼、お返しとして考えました。
最初の着想はそこにあるわけです。しかし、同時に物語を動かす人物が見えて来ると、そこに戦争が重なって来ました。縦には時間的に、横には今も世界の各地で、現在の日本では想像もできないような悲惨なことが行われています。そうすると、家庭内暴力を受ける弱者としての女性の姿も見えて来ました。理不尽な行為に傷つく者が、なぜいるのか。
そういう思いは、「こういうタイプのミステリ」に、決してふさわしいものではありません。功利的にいうなら、そこで舵を別の方向に取るべきでしょう。しかし、物語というのは作者ですら、自由に形を変えられるものではないのです。全て、必然から生まれるといっていいでしょう。
自然に、これは盤上の出来事というーーつまり、寓話という形を取ることになりました。ここにあるのは生きた人間のからみあいというよりは、白と黒との、打たれる者と打つ者との原始からある闘いの図式です。どうしようもない苛酷な運命や状況を描こうとした結果、この物語は、心を休めたいという方には、不向きなものとなりました。読んで、傷ついたというお便りをいただきました。女の方です。そういう方がいらっしゃるのは、とてもつらいことです。一方で、様々な方から思いがけないほど高い評価をいただくこともできました。
ノベルスは、より多くの方の目に触れる媒体です。読んでよかったという方が増えるのは嬉しい。しかし、逆のことは望みません。あらかじめ、お断りしておきたいのです。今、物語によって慰めを得たり、安らかな心を得たいという方には不向きですーー(北村薫)
この前書きは僕を戸惑わせました。『盤上の敵』は「怖くないミステリー」ではなかったのか、なぜ「怖くないミステリー」を読んだ読者が「傷ついた」と言って作者に手紙を寄越すのか、よく理解できませんでした。
今は、この疑問について僕なりの明確な答えを持っています。その答えについて書く前に本の内容の紹介をしましょう。物語は、猟銃の免許を取った瀬川章一郎という人物が早朝に鴨撃ちにでかけ交通事故を起こしてしまうところから始まります。
車の右で、ゴツンという音がした。同時に、自転車に乗った影が崩れ、地に沈んだ。
(中略)
闇に向かって流れ出しているのは、車内灯の光だ。そのせいで車の周囲は、深海に海中電灯を落としたように、ぼんやりと明るくなっている。
章一郎に、相手の顔が初めて見えた。
若い男だ。二十前後に見えた。唇は厚く、眼は細い。濃い眉が、はっきりとした逆八文字で、眉間のところに、眼と眉の作る四本の線が集まるような感じだ。その眼の鋭さに、いいようのない威圧感があった。
――怒っているのか。
章一郎が感じたのは、腹が落ち着かないような恐怖だった。近づいて来る男は背も高くないし、肩幅も広くはない。それなのに、上から大きな手で押し付けられたように気になる。
章一郎は仕事柄、重いものを持つのには慣れていた。人並みの力はあるつもりだ。だが、気の強い方ではない。子供のように逃げ出したくなった。自分は座っていて、あちらは立っている。そのせいで、気圧されるのだろうか。
男は、章一郎の服装を見た。友達にアドバイスを受けて整えた猟服である。
「釣りかあ?」
章一郎は、一瞬、相手が何をいったのか分からなかった。そして、自分の服装のせいだと分かった。「遊びのために急いで、引っかけたのか」と責められたような気がした。
「いや」
「何だよ」
「ちょっと、――その鴨を撃ちに」
こんなことは関係ないと思いながら、つい柔順に答えてしまった。
気のせいか、男の眉が、わずかに動いたような気がした。
男は、そのまま近寄って来た。殴り掛かられるような気がしたが、そんなこともなかった。
章一郎は、相手が普通に歩いているので、安心した。一言謝ればそれですむかも知れない。法律上はまずいことだろうが、先を急いでもいる。一万円も渡せば、ことは終わるかも知れない。それでは少ないだろうか。
――そこで、章一郎は「向こうから、こっちのライトが見えなかった筈はない」と思い当たった。どうして、左の路肩に寄るなり、しなかったのか。自転車のブレーキが壊れていたのか。
人によったら、逆に自転車の相手に「車を擦った」と詰め寄るところではないか。
男は、裾に泥のついたジーパンをはいていた。その左足を、章一郎の目の前で、いきなりくの字に曲げた。そして、荒く息をついた。口から白い煙が吐き出された。
「……膝」
男は、そういいながら、左手で膝を揉むようにした。上には黒いジャンパーをひっかけていたが、手袋はしていなかった。
「膝を?」
章一郎が、「――痛めたのか」といいかけた時に、男は当たり前のように後部座席のドアを開いていた。ぞくりとした。
「――あの?」
男は、間髪を入れず、いった。
「警察、行こう」
そう聞いて、章一郎は安心した。得体の知れぬ相手だが、自分から「警察」といい出すのなら心配ないだろう。怪我も大したことはなさそうだ。後で面倒が起きないように、病院にも行かせた方がいいのかも知れない。その辺のことは、警察でアドバイスしてくれるだろう。
「自転車は?」
「置いてきゃいい」
(中略)
章一郎は、男に言われた通り、車を元の道に返した。「わずか十分ほど前には、何の心配もなく、ここを来たのに」と思う。それこそ、思い掛けぬ銃弾を受けた鴨のようだ。
陸橋から大分離れた、闇の一段と濃い辺りで、突然、男がいった。
「停めてくれよ」
「え?」
「気持ち悪い」
小刻みに一、二度、振り返って見ると、男は顔を伏せている。口を押さえているようだ。後ろ頭の、ぼさぼさの髪の毛が立っていた。打ち所が悪かったのか。今頃になって吐き気がして来たのか。
章一郎は、あわてて、車を土手に寄せて停めた。
サイドブレーキを引いて、振り返りかけた時だった。目の前を、ひゅっと何かが動いた。次の瞬間、じわっと細い蛇がまとわりついたような圧迫を感じた。あっと、指でつかむ。
電気のコードらしかった。
「な、なーー」
「何をする」というのも、言葉にならなかった。男は、緩慢とも思える動作で、ゆっくりそれを締めて行った。章一郎は、自然、シートに背を押し付けた形になる。拝むようにコードにかけた手には、さして力が入らない。突然、襲って来た今の状況が、章一郎には飲み込めなかった。ただ、喉を締め付ける紐の存在だけは現実だった。神経の作用によるものか、砂を撒いたような光が、閉じたり開いたりする目の前で点滅した。
「か、金なら、やっ」
――やる、といいかけて、語尾がつぶれた。金が目当てなのだろう。車を取られてもいい。何とか逃げ出したかった。いつもなら、今頃はまだ、布団の中で寝ているのだ。どうして、こんなことが自分の身に起こるのか。信じられなかった。
章一郎は、そこで、あっと思った。
――ここで死ぬのか。
いつかは来る筈の時だ。だが、どうして、それが今なのか。そんな馬鹿な、と思うと、章一郎の眼に突然、涙が溢れた。
このあと章一郎は、信じがたいような無惨な殺され方をします。第一部を読んだだけで、これは紛れもなく怖い小説であることがわかります。今回ばかりは川上弘美の感じ方に共感を覚えることができませんでした。確かにこれなら「傷ついた」という手紙を寄越す読者もいるだろうと納得しました。『盤上の敵』は本当に恐ろしい小説です。そこには、作品の中の言葉を借りれば、「大きな悪意そのもの」が描かれています。ならばなぜ僕はこの本をみなさんにお薦めするのか。一つには世の中にある「悪」や「闇」に勇気を持って目を向け、その存在をはっきり認識したうえで、物事を考えることが大切だと考えるからです。もう一つは、解説者の光原百合さんが書いている通り、この小説の大きなテーマが「再生への祈り」であるからです。作中人物の再生だけでなく、世の中のあらゆる理不尽な悪に倒れた人々の再生を祈る物語です。『盤上の敵』は極めてリアルな物語でありながら、一つの寓話とも読める不思議な作品なのです。
文庫の最後に載っている光原百合の解説はすばらしいと思いました。特に最後の五行には心からの共感を覚えました。その部分を引用して「昨日の新聞から217」を終わりたいと思います。
解説者としても、これから読む読者が傷つく可能性を否定することはできない。私自身、この小説に登場する底知れぬ闇に対して感じた恐怖を、いまだに忘れられない。だが未読の方には、できることならその心構えをしたうえで、やはりこの小説を読んでほしいと思う。
私にとつては生涯忘れ得ぬ傑作だから。
再生への祈りを共に祈ることができて、よかったと思っているからーー。