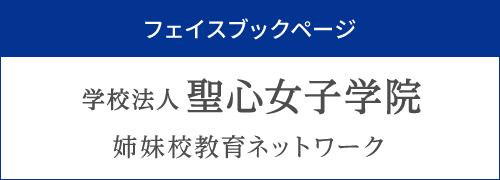フィールド日記

2018.02.28
築山の白梅
紅梅よりだいぶ遅れましたが、築山の白梅も満開に近づいています。写真を撮ることはできませんでしたが、目視で訪花するヒラタハナアブの姿も確認できました。啓蟄を待たずに虫たちも動き始めたようです。

今日のことば
『随想 春夏秋冬』(宮城谷昌光・新潮文庫)を読む
― 『小倉百人一首』と『水無瀬三吟百韻』を貫くもの ―
連歌師の宗祇は文亀二年(一五〇二)七月晦日に箱根湯本で亡くなります。宗祇の遺体は箱根で葬られることはなく、一行はさらに旅を続けました。『宗祇』(奥田勲)には次のような一節があります。
箱根山を生きた姿のように輿に乗せられて越えた宗祇は、八月三日の明け方、相模駿河の国境に近い桃園の定輪寺(静岡県裾野市桃園)に埋葬された。富士山をもう一度見たいという越後を出発するときの希望を、富士の裾野の寺に埋葬することで宗長は果たしたのであろうか。寺の門前の少し引っ込んだ所で、水が流れ、杉・梅・桜の木のあるあたりに亡き骸を納めて、生前、塚には松を印にしてほしいと話していたことを宗長は思い出し、松を一本植え、卵塔を建て、仮の垣根をめぐらした。そこに七日ばかり籠って弔い、一行は駿河の国府へ出た。
不二聖心女子学院の生徒は皆、登校する際にバスでこの定輪寺の近くを通過します。桃園橋の交差点には宗祇の句碑もあり、私たちは宗祇を身近に感じることのできる環境で生活しています。先日、二〇一七年に文庫化された宮城谷昌光の『随想 春夏秋冬』(新潮文庫)を読んでいて、富士山麓に縁の深い宗祇に関係する「連歌」という題の随想を見つけました。その文章を次に引用します。
記憶のなかにたしかにありながら、いままで書かずにきたことが多いことに、いまさらながらおどろいている。
大学の一教室の光景も、そのひとつである。
その教室は、古い校舎のなかにあり、聴講に集まる学生は多くなかった。人気のある教授の講義が行われる教室は、新しく、しかも広い。それにくらべると、その教室はじみであった。はじめてその教室にはいった私は、あたりをみまわして学生の数を数え、落ち着かず、
――選択をまちがえたかな。
と、早くも悔やんでいた。
やがて、あらわれた教授がすでに壮年をすぎていることはあきらかであり、もの静かであることにも、ひそかに落胆した。はつらつとした講義を聴きたかった私は、この教室でのたいくつさを予想し、
――この教授の講義を、一年も聴くのか。
と、うんざりした。国語の授業である。与えられたテキストは、
「連歌(れんが)」
であった。これも、じみであった。短歌でも俳句でもない歌に関心はなかった。
ところがである。その教授の講義を、一回、二回、三回と聴くうちに、私の心のなかに変化が生じた。連歌のおもしろさを知りはじめたと同時に、この歌の世界をこれほどやさしく説けるこの教授は、尋常な人ではない、と気づいたのである。
「稲垣達郎(いながきたつろう)」
これが教壇に立っている人の氏名である。(中略)
稲垣先生から与えられたテキストは、すでに失ったが、連歌の冒頭の句は、忘れていない。
雪ながら山本かすむ夕べかな
『水無瀬三吟百韻(みなせさんぎんひゃくいん)』にある宗祇の発句である。この発句こそ、日本で最高の連歌集の冒頭に置かれたもので、連歌史上、これを踰(こ)える発句はない。句の意味は、こうである。峰にはまだ雪があるのに、その麓には春霞がかかって、夕べの紅に染められている。私がこの発句をはじめて読んだとき、なるほど絵画的ではあるが、さほど非凡な句ではない、と感じた。が、稲垣先生の説明をきいて、目から鱗が落ちたおもいであった。
「最初に、雪、を置かねばならぬのです」
稲垣先生の断定である。
――なぜ。
私は心のなかで問いの声を発した。ここから稲垣先生の解説に吸いこまれてゆく自分があった。そこでの説明を、ここで正確に再現するには、記憶に濃淡がありすぎる。が、私見をまじえれば、こうである。
六十八歳の宗祇が弟子のふたりとともに、水無瀬の御影堂(大阪府島本町)において、連歌の会を催したのは、長享二年(一四八八年)の正月二十二日である。じつはその年は、歌道に精通し、歌人の最大の庇護者であった後鳥羽上皇が、隠岐島で崩御されてから二百五十年目にあたった。すなわち上皇の二百五十年忌にあたって、上皇の離宮跡に建てられた御影堂に奉納したのが、その百韻である。
発句は、いつ、どこで詠まれたか、ということがわからなければならない。季節は、冬から移ってきたばかりの春である。そこで宗祇は、まず雪を置いた。つぎに霞をだした。この霞は後鳥羽上皇の歌のなかにある。
見渡せば山本霞むみなせ川 夕は秋と何思ひけむ
山本かすむ、と詠めば、水無瀬であることがわかるしかけになっている。私のおどろきはひろがるばかりであった。
この随想の中に登場する後鳥羽院が、実は百人一首の成立に深い関わりを持ったという説を織田正吉が『百人一首の謎』などの著作で唱えています。百人一首を編んだ藤原定家は承久の乱で隠岐に流された後鳥羽院の呪いを恐れており、後鳥羽院への鎮魂の思いを百人一首という歌集に込めたと織田正吉は考えたのです。
隠岐に流された後鳥羽院の呪いを定家が恐れていた可能性について織田正吉は次のように述べます。
隠岐に流された後鳥羽上皇の呪詛については、承久の乱から六年目、すでにその風評が流れていた。『明月記』(定家の日記)嘉禄元年(一二二五)六月一三日の条には、「琵琶湖畔の志賀浦に四足で青黒く大きな怪鳥が多数現われ、数日のあいだ、人が争ってそれを取り、その鳥を食べた者は即死した。鳥は『隠岐の掾(じょう)』と呼ぶ」と書いている。「隠岐の掾」は隠岐の国司、すなわち後鳥羽上皇のことである。
定家は『新勅撰和歌集』の撰進で幕府におもねる撰歌をした。そのことを咎めるかのように、『新勅撰和歌集』撰歌の最中に九条家と関係深い皇族三人の死が続く。神経が繊細で、つねに病気におびえ、しかも高齢の定家が冷静でいられるはずはないのである。定家が上皇の呪詛に恐怖をおぼえたという想像は大きくはずれてはいないだろう。
この仮説が正しいことを、百人一首のさまざまな歌を挙げて織田正吉は例証していきます。たとえば「心あてに折らばや折らむ初霜のおきまどわせる白菊の花」の「白菊」は後鳥羽院が好んだ花であり、数ある菊の歌の中でこの歌が撰ばれたのは、歌の中に「おき=隠岐」が詠まれているからだと織田正吉は説きます。このような例を多数挙げた上で次のように結論づけます。
『百人一首』は定家が後鳥羽上皇の呪詛(じゅそ)を恐れ、鎮魂の思いを秘めた歌集である。
後鳥羽院ゆかりの場所に自作を奉納した宗祇は、箱根湯本で亡くなった夜にひどく苦しみ同行者が揺り動かすと「たった今の夢に定家卿に会い奉った」と語ったという記録が残っています。後鳥羽院も定家も宗祇の生涯の中でたいへん重要な位置を占めている人物たちであることは間違いありません。御影堂に『水無瀬三吟百韻』を奉納する際、宗祇が後鳥羽院の悲運を改めて思い起こした可能性はゼロではないでしょう。宗祇の『水無瀬三吟百韻』の奉納もまた、二百五十年の時を超えた鎮魂の行為であったと言えるかもしれません。