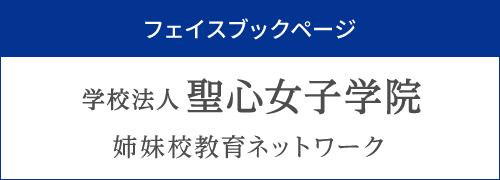フィールド日記

2016.12.08
今朝の富士山
今朝の富士山の写真です。

今日のことば
先月、藤原ていさんが亡くなりました。藤原ていさんは、富士山を舞台にした作品を数多く残した新田次郎の奥様です。
以下に掲載するのは、藤原ていさんの代表作、『流れる星は生きている』の紹介文です。
平成二十年四月十一日(金)の読売新聞に哲学者梅原猛と数学者藤原正彦の対談が載りました。対談の一番最後は藤原正彦の言葉で終わっています。梅原猛の、人類が滅びる要因は、自然破壊、核戦争、内面の崩壊の三つあって、その危機がいよいよ深刻になってきたという発言に対して次のように藤原正彦は答えています。
藤原 やはり、何かにひざまずく心がないといけませんね。日本人は太古の昔から、人間なんて自然のほんの一部だと、非常に謙虚だった。人間と自然が一体になった日本の自然観は、今後ますます大事になっていくでしょう。だから日本が、この素晴らしい文化を世界に広めていくことこそが、大きな国際貢献になる。どしどし世界に発信していくべきだと思う。
やはり藤原正彦はいいことを言う、対談を読んでよかった。素直にそう思いました。
対談を読んでよかったという思いには、実は特別な意味が込められています。一カ月前の自分だったらおそらくこの対談を読んでいなかっただろうという思いがあったのです。僕は長い間、藤原正彦という人を尊敬し、特にその著書『遥かなるケンブリッジ』はかけがえのない愛読書であった時期もあり、かつて不二聖心で講演をしていただいたこともあるという縁から特別な親しみを感じてもいたのですが、『国家の品格』がベストセラーになって以来、あまりにも名前を目にする機会が増え、正直少し敬遠する気持ちが生まれていたのです。しかし、先日たまたま藤原正彦の母、藤原ていの『流れる星は生きている』を読み、初めて藤原正彦の原点とも言える体験を知って衝撃を受けて以来、もう藤原正彦という名前が頭から離れなくなってしまったのです。
「たまたま」と書きましたが、それは、書店で「忘れられない本 中公文庫BIBLIOフェア」というフェアをやっていて、「忘れられない本」の一冊として『流れる星は生きている』が平積みになっていたということなのです。何十年もの間、いつか読まねばと思い続けてきた本をついに手に取るきっかけとなりました。本の帯には「母の遺した昭和20年8月の壮絶な手記」とあります。表紙にはあらすじが次のように書かれています。
昭和二十年八月九日、ソ連参戦の夜、満州新京の観象台官舎――。夫と引き裂かれた妻と愛児三人の、言語に絶する脱出行がここから始まった。敗戦下の悲劇に耐えて生き抜いた一人の女性の、苦難と愛情の厳粛な記録。戦後空前の大ベストセラーとなり、夫・新田次郎氏に作家として立つことを決心させた、壮絶なノンフィクション。
帯にも表紙にも使われている「壮絶」という文字。この文字がこれほどふさわしく使われている例を僕は知りません。『流れる星は生きている』は「壮絶」という表現が本当にぴったりくるノンフィクションでした。戦争について少なからず自分は学んできたつもりでしたが、この本を読んで何と自分は無知であったかと愕然としたのです。戦争が人間にどれだけの深い苦しみを強いるものであるか、僕は改めてこの本で学びました。第二次世界大戦が昭和二十年八月十五日で終わったというのも、一面的な歴史理解に過ぎないということもわかりました。『流れる星は生きている』の作者藤原ていにとって、本当の苦しみは昭和二十年八月十五日に始まったのです。
満洲から朝鮮半島を経由して日本に引き揚げる帰途、三十八度線を目の前にして極限の苦しみと闘う家族の姿を引用してみましょう。
「逃げるんだ逃げるんだ、逃げおくれると私たちは殺される」
私は三十八度線まで、こう心を叱咤しながら歩いた。でもいま冷静になって考えると、その時、それほどおそれた私を追ってるものの正体がわからない。長い間、聞いていた先入観が私を完全に悪魔のとりこにしていたに違いない。
この時は、こう確信していた。「早く逃げないと殺される」そう思いこんでいた。
正広は間もなく、めそめそ泣きだした。
「お母ちゃん、歩けない」
正広のことなんかかまっていられない。(中略)
私は前の影を追うことだけしか考えない。頭の中が妙に空白になっていながら前進するということだけが激しく私を支配して、歯を喰いしばり、正広(長男)と正彦(次男)をどなりつけていた。
「正広、なにをぐずぐずしている!」
「正彦、泣いたら、置いて行くぞ!」
私はこの時初めて男性の言葉を使っていた。自覚しないで私の口をついて出てくるものは激しい男性の言葉であった。
道が坂になった。二歩登っては、一歩すべる、正彦が「ひいッ! ひいッ!」と泣く声が風にちぎれて飛んでゆく、私は正彦の尻を力いっぱいたたきながら、よろける正広をどなりつけて登って行った。
やっと、坂を登りきった頃、ほのかに明るさがさして来て夜は明けて来た。私の登ってきた道は一間ぐらいの幅の道で、両側は見渡す限りの禿山であった。禿山といっても木がないだけで草は道の両側に生い茂っていた。私が道を間違えずにここまで来たのは、いくらか道が低くなっていたからだった。私は自分の姿を見てびっくりした。それより二人の子供の姿はひどかった。赤土の泥を頭からかぶって、上着もズボンも一晩のうちに赤土の壁のようによごれていた。かろうじて、眼だけが光って、もう泣く涙はないのか、つんのめり、つんのめりして前へ進んでいった。正彦は一晩の難行のために両方の靴をなくしていた。そして赤土の手で眼をこするから前が見えなくなる。
「お母ちゃん、見えないよう」
と泣く。
「馬鹿!」
私は思いきって前へ突きとばしてやると、まだ起き上る元気はあった。よろよろと赤土の泥の中から立ち上って、あきらめたように一歩二歩前に進んで終に倒れてしまう。起きられないと見て私は正彦の左手を引っ張り上げて、引きずって前へ前へと前進した。ズボンの膝から下をずるずる泥の中に引きずりながら。それでもまだ立とう立とうとする意志があるらしく、いくらか引きずる手が軽くなる時があった。
正広は私の悲壮な努力を見て、そう泣かなかった。黙ってついて来た。おくれそうになると私に、
「馬鹿、そこで死んでしまいたいか」
と怒鳴られては苦しそうな眼を私に向けていた。(中略)
私は咲子を背中に負う時によく顔を見てやった。顔は痩せて小さく、うつろな眼をあけていた。私はリュックの中から赤い紐を出して腰にしっかり結んだ。
私は最後の時が来たらこの紐で子供たちを殺し自分も死のうと考えていた。
眼の前に大きな山が見える。道はその山に向かって続いている。
「あの山、あの山を?」
私にはその力がない。どうせ死ぬなら死ぬところまで行って死ねばよい。私は勇気を出して立ち上った。
「お母ちゃん、歩けない」
正彦がはだしのままで立ち上って泣きだした。
「馬鹿! 死んじまえ、馬鹿!」
私は正彦の頬を平手でぴしゃりと打った。こうして自分の気持ちを昂奮させて狂ったようになりながら前へ前へと行かなければならない。
このような壮絶な場面がまだまだ続きます。というより、全編が壮絶な場面の連続と言ってもいいのかもしれません。満州から引き上げてきた日本人の肉体的な苦しみがこれほどまでにひどいものであったことを僕は初めて知りました。しかも、引き上げの途中で味わった苦しみは肉体的なものだけではなかったのです。日本人はいくつかのグループに分かれて満州から朝鮮半島を通って日本を目指しました。極限状態に置かれたグループの中では、少しのきっかけで争いごとが起こります。するとそれまで仲間だと思っていた人たちがエゴとエゴとをぶつけあい、醜く争い始めるのです。これこそが戦争の悲劇だと思いました。自分の一番醜いところをさらけださなければ生きていけなかったのだと思います。この辛さは日本にたどりつく直前まで続きました。釜山を目指して乗った列車の中で藤原ていは子供たちの下痢に悩まされました。着替えを持っていないので、下着を汚してもかえることができません。夏の暑さも手伝って臭気は車内に充満し、他の乗客は不快感を露わにします。
私の筋向こうに一団の家族がいた。年頃の娘を三人つれた夫婦であった。この男が最もひどく私をせめた。
「なんとかなりませんか、臭くって皆迷惑してますよ、え、早くなんとかしなさい」
「すみません、汽車が駅へ着いたらすぐ綺麗にしますから」
「汽車が駅へ着くって、いつのことか分らないじゃないですか。何とかしなさい、人の迷惑を少しは考えたらどうです」
「はい、でもこの子のパンツはこのはいているもの一枚しかありません、これを捨てたらもうはかせるものがないんですの。すみません、我慢して下さい、駅へ着いたら洗って来ますから」
「わからない人だねえ、私はそんな言いわけを聞いているんじゃない、あんたは一体公衆道徳っていうものを知らない人だね、え! 人の中で子供に糞をひらせて、しゃあしゃあしているなんて、よくお母さんらしい顔をしていられるもんだね」
この男はそういって自分の奥さんの方を向いて、そうだろうという風にあごをしゃくり、娘たちの方を向いて、
「見ろ、あの女を」
といった風な極度に軽蔑した態度を示していた。三人の娘はこっちに大きなお尻を向けていて、そのお尻をいかにも汚いものでもよけるように持ち上げて、および腰になったまま、苦い顔をして私を見つめていた。
私はその娘の眼を見ると抑えつけていた激しいものがせきを切ったようにどっとあふれて出た。
「わからない人はあなたじゃないの。私たちは初めからこんなにみじめではなかったんです。私の今こんなに困っているところを見てみんなで軽蔑して、皆でいじめつけてそれがあなたの公衆道徳ですか。私はこの子のよごれたパンツを丸めて捨てて、新しい乾いたものに取り替えてやりたいのは山々です。私だって私だって、殺されるように苦しい思いをしているんですよ。皆さんに気兼ねして、御覧なさい、この子もこんなに小さくなっているじゃありませんか。どうしたらよいの、どうしたらよいか私に教えて下さい」
その男は黙ってしまった。そして横を向いて一番大きい娘にいった。
「文子、お前のなにかをくれてやれよ」
その娘はごそごそと大きなリュックの中を探し始めた。
「よして下さい、そんなもの、私は戴きたくはありません。あなたなんかに、死んだって恵んで貰うもんですか。私は物乞いじゃありません。もしあなたにほんとの公衆道徳があったら、黙って臭いを嗅いでいなさい」
私は涙の中にこれだけいうと、自分の責任のようにせつない顔をして私を見上げている正広にいった。
「正広ちゃん、いいんだよ、いいんだよ、今に汽車が止まったら綺麗に洗ってあげるからね」
そういって泣き伏してしまった。貨車の中は静かになった。全部の人が私を見詰めている複雑な批判の下で、私は子供を連れている悲哀をつくづく感じた。
この男もそんなに悪い人ではないのかもしれません。しかし戦争は人間を変えます。自分の一番醜い部分と向き合いながら生きていかなくてはなりません。この本の中にはそのようなむごい現実が生々しく描かれていますが、藤原ていは他人を非難するだけではないのです。自分のとった醜い行動についてもすべて正直に書いています。それもまた時として「壮絶」という言葉が当てはまるほどの醜さなのです。
私たちの生きている時代は、苦難に満ちた戦争の時代のあとに位置する時代であり、私たちの享受する平和は多くの日本人の犠牲の上に築かれたものであることをやはり忘れてはならないのでしょう。その意味でこの一冊を読むことは今を生きる私たちの一つの責任であるとも思えてくるのです。
時々、自分にあり余るお金があったら、不二聖心の生徒全員分を購入して一人一人に手渡したいと思う本に出合うことがあります。『流れる星は生きている』はまさにそのような本でした。この推薦文は、まだまだ、この本の持つすさまじいまでの迫力を伝えきれていません。
どうぞみなさん、手にとってすべてを読んでみて下さい。