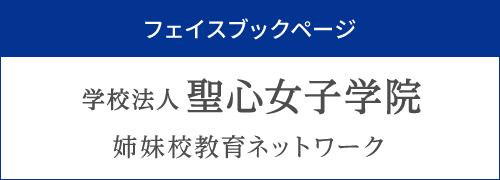フィールド日記

2016.09.03
アンネのバラ
図書館の近くの花壇に「アンネのバラ」が咲いていました。
1959年にヒッポリテ・デルフォルヘ氏によって作出されたバラが、亡きアンネ・フランクに捧 げられ、それ以来、そのバラは「アンネのバラ」として世界中の人々に愛されるようになりました。「もし神様がわたしを長生きさせて下さるなら、わたしはつ まらない人間で一生を終わりません。わたしは世界と人類のために働きます。」という言葉を残したアンネ・フランクに捧げられたバラは、まさに「平和のシン ボル」と言えるでしょう。


今日のことば
昨日の新聞から193 平成二十二年四月二十六日(月)
『思い出のアンネ・フランク』(ミープ・ヒース 文春文庫)を読む
―― 人間としての真実の美しさが映し出されている人に出会う ――
2010年2月10日の朝日新聞の夕刊の「惜別」のコーナーに、ミープ・ヒースさんの記事が載りました。その全文をまず引用してみたいと思います。
ミープ・ヒース 1月11日死去(転倒による首のけが)100歳 1月18日葬儀
第2次大戦中のアムステルダムで、アンネ・フランク一家がナチスのユダヤ人迫害から逃れた「隠れ家」のくらしを知る、最後の証言者だった。
香辛料輸入会社を経営していたアンネの父オットーの秘書だった。自身の夫ヤンや同僚3人と、会社の倉庫裏につくられた隠れ家に食料や本を届け、一家ら8人の生活を支えた。1944年に一家が連行された後、ひそかに隠れ家に戻りアンネの日記を保管した。
翌年、オットーが強制収容所からただ1人生還し、アンネの死を知る。それまで日記は読まず、会社の机の引き出しにしまっていた。「子どもであれ、プライバシーが尊重されるのは同じ」。アンネが戻ったら渡すつもりだった。
ユダヤ人をかくまっていると分かれば強制収容所に送られる危険もあった。「私は英雄ではないし、特別なところのない人間です。その時に必要だと思ったことを喜んで引き受けただけ」と繰り返していた。フランク一家にも隠していたが、自宅でもユダヤ人学生をかくまっていたという。
ウィーン生まれ。第1次大戦でオーストリアの食糧事情は悪化した。子どもの一時受け入れを決めたオランダに11歳で渡り、預けられた家庭で養子になった。「5人の子どもがいて給料は低かったが、彼らはすべてを私と分け合ってくれた」
60年に「アンネ・フランクの家博物館」が開館した。子どもの案内役を引き受けるなど、積極的にかかわり続けた。
同博物館収蔵品部長のテルシン・ダシルバさんによると、長男一家の近所で一人暮らしを続けた。99年に脳梗塞で言語に障害が残ったが、死の直前まで、世界中から届く年間650通ほどの手紙に目を通し、家族や友人に代筆を頼んで、できるだけ返事を書いた。
新聞2紙読み、世界で何が起きているかを常に気にしている人だった。(井田香奈子)
ミープ・ヒースさんは、アンネと過ごした日々の記録を『思い出のアンネ・フランク』という本にまとめました。体験した人でなければ書けない歴史的な瞬間の数々をミープ・ヒースさんの優れた文章で読むことができる本です。例えば、引用した「惜別」の文章には「ひそかに隠れ家に戻りアンネの日記を保管した」とありますが、アンネが連れ去られた直後に隠れ家に入って日記をかき集めた時の様子が、この本の中には詳細に記されています。次に引用してみましょう。
それからわたしはフランク夫妻の寝室へはいっていった。そこの床の上、乱雑にほうりだされた紙や書物の山のなかに、赤とオレンジ色の格子縞の、布表紙の日記帳が落ちているのが目にとまった。アンネが十三歳の誕生日に父親からもらったものだ。わたしは目顔でエリーにそれをさししめした。わたしの合図を受けて、エリーはかがみこんでそれを拾い、わたしに手わたしてよこした。アンネが日記帳をもらって、どんなに喜んでいたが思いだされた。胸のうちのひそかな思いを書きつづったこの日記帳が、アンネにとってどれだけだいじなものだったかも知っていた。ほかにもアンネの書いたものはないかと、床に散乱したがらくたをざっと見まわすと、彼女が格子縞の日記帳を使いきったあとで、エリーやわたしがあげた使い残した帳簿のほか、たくさんの筆記用紙が見つかった。エリーはいまだにひどくおびえていて、たえずわたしをうかがって指示をもとめていた。そこでわたしは彼女に言った。「手伝ってちょうだい。アンネが書いたものを集めるのよ」
手ばやくわたしたちは、アンネのくずした筆跡で埋まった紙を両手いっぱいにかきあつめた。
この『思い出のアンネ・フランク』は世界中の多くの人に感動を与えました。芥川賞作家の小川洋子もその一人で、彼女は実際にミープ・ヒースに会い、ミープ・ヒースについてのエッセイを何度か発表しています。その中の一編を紹介しましょう。
『アンネの伝記』(メリッサ・ミュラー著 畦上司訳)を手に取った時、一番に目についたのは、ミープ・ヒースさんの文章が後書きに添えられている点だった。お元気でいらっしゃる様子がうかがえ、うれしかった。
ミープさんはオットー・フランクが経営する会社の従業員で、夫のヤンさんともども隠れ家の住人たちの命綱だった。
一九九四年初夏、アムステルダムのご自宅へインタビューに伺った時の思い出は強く残っている。もう既に八十の半ばでいらしたが、老いた雰囲気はなく、きちんとしたスーツ姿で、真っすぐにこちらを見やりながら、「さあ、何でもお聞きなさい」とおっしゃった。
ミープさんには、特別なことをやったという意識がなかった。言葉は少なく、常に冷静で、日記を救った功績の大きさをいくら私が称えても、決してその称賛を受け入れようとはしなかった。気負いなくただ、人間として当然なすべきことをやったにすぎない、と繰り返すのだった。
最も困難な時代、人間が神に試された時代、なすべきことを正しく見抜き、夫ともに命をかけて友人たちを守った一人の女性が、今はアムステルダムの小さなアパートで、慎ましくひっそりと年を重ねているーー目の前に座ったミープさんを見つめながら、私はそこに人間としての真実の美しさが映し出されているような気がした。
インタビューが終わり、ミープさんとお別れのキスをして、アパートの階段を降りる時、訳も分からず涙が出そうになったのを今でもよく覚えている。
『アンネの伝記』の後書きに、ミープさんは印象的な一行を記している。
……私にはアンネの命を救うことはできませんでした……
私はそこに衝撃を受けた。彼女の心の根底を占めていたのはこれだったのか、とようやく気づいた。彼女にとって、ユダヤ人をかくまった、日記をドイツ軍から救い出した、という事実など、大事な友人たちの死の前では意味をなさなかったのだ。
私はインタビュアーとして失格だった。功績に気を取られ、戦後五十年以上彼女が抱え続けなければならなかった苦しみについて、思いやれなかったのだから。あの時泣きそうになったのは、ミープさんの悲しみに身近に触れたせいだったのかもしれない。
これほどの善をもってしても、アンネの命が奪われるのを止められなかった。自分がどれほど残酷な時代を生きているか、思い知らされる。
『思い出のアンネ・フランク』という本自体が、「ミープさんの悲しみ」の結晶のような本なのですが、とりわけ悲しいのは、戦後の、アンネの帰還を待つ日々を記した部分だと思います。父親のオットー・フランクは最後までアンネと姉のマルゴーが解放されて無事に帰ってくることを信じて疑いませんでした。
フランク氏はつてを頼って、ベルゲン・ベルゼン(アンネのいた収容所)にいたと言われる人たちに手紙を出していた。口伝ての情報を通じて、日ごとに人と人とのネットワークがひろがっていった。フランク氏は、毎日それらの人たちからの返信を待ちわび、生存者の名簿が発表され、貼りだされるのを待ちわびた。ドアにノックの音がしたり、階段に足音が聞こえたりするつど、みんなは心臓が止まる心地がした。ことによると、とうとうマルゴーとアンネとがここにたどりついたのかもしれない。とうとうこの目で彼女たちのぶじな姿が見られるかもしれない。六月十二日には、アンネの十六回目の誕生日がこようとしていた。ひょっとすると、その日までには……けれどもやがてその日がきて、また去っていっても、依然としてなんのニュースもなかった。
(中略)
ある朝、オフィスにはフランク氏とわたしだけがいて、それぞれ郵便物を開封していた。フランク氏はわたしのそばに立ち、わたしは自分のデスクにすわっていた。かたわらで一通の手紙が封を切られるのをおぼろげに意識していたが、そのあと、一瞬の静寂があり、なにかがわたしの目を、手もとの手紙からひきはなした。そのとき、オットー・フランクの声がしたーー抑揚のない、完全に打ちひしがれた声。「ミープ」
わたしの目が彼の目を見あげ、その目をさぐった。
彼は両手で一枚の便箋を握りしめていた。「ミープ、ロッテルダムにいる看護婦さんから返事がきた。ミープ、マルゴーもアンネも帰ってこないよ」
そのままわたしたちは凝然と見つめあった。ふたりとも、雷に打たれて、魂の奥底まで焼きつくされてしまったようだった。やがてフランク氏が社長室のほうへ歩きだしながら、あの打ちひしがれた声で言った。「奥のオフィスにいる」
彼が部屋を横切って、廊下づいたに奥へ行き、やがてドアがしまるのをわたしは聞いた。
わたしも完全に打ちのめされて、ぼんやりデスクにすわっていた。これまでは、どんなに悲惨なニュースを聞いても、なんとか受けいれることができた。好むと好まざるとにかかわらず、それを受けいれざるを得なかった。しかし、きょうのこのニュース、こればかりはなんとしても受けいれられなかった。それだけはぜったいに起こらない、そう確信していたまさにそのことが起こったとは。
ほかの社員が出勤してくるのが聞こえた。ドアがあき、陽気な話し声がした。つづいて、おはようという挨拶、コーヒーカップのかちゃかちゃ鳴る音。ふいにわたしはデスクの袖のいちばん下の引き出しに手を入れると、もう一年近く、そこでアンネを待ちつづけてきたあの日記類をとりだした。わたしも含めて、だれひとりそれに手を触れたものはいなかった。そしてもはやアンネは、ついに自分でそれをとりにもどってくることはないのだ。
引き出しに入っている紙の束を洗いざらいとりだすと、そのいちばん上に、あの小さなオレンジ色の格子縞の日記帳をのせ、フランク氏のデスクにおもむいた。
フランク氏はデスクにむかってすわっていた。ショックがその目を暗くうつろにしていた。わたしはかかえてきた日記帳その他をさしだした。そして言った。「さあ、これがお嬢さんのアンネの、おとうさまへの形見です」
彼がその日記帳に気づいたのがわかった。三年とちょっと前、「隠れ家」にはいる直前に、アンネの十三回めの誕生日の記念として与えたものだ。彼は指先でそっとそれに触れた。持ってきたいっさい合財を彼の手に押しつけると、わたしは部屋を出て、そっと扉をとざした。
そのあとまもなく、わたしのデスクの電話が鳴った。フランク氏の声がした。「ミープ、しばらくだれにも邪魔されないようにしてくれないか」
「もうそのようにとりはからってあります」と、わたしは答えた。
このあとしばらくして、アンネの日記は出版されることになるのですが、それでもミープさんは日記を読むことをしませんでした。第二版が出て初めてミープさんは日記を手にとります。ミープさんは、日記を読み終えて、これはアンネがこの世界に遺したすばらしい遺産だと感じたと書きます。そのあとでさらに次のように続けます。
たとえアンネの日記がけっしてこの世に出ることがなかったとしても、それよりはアンネやほかの人たちが、なんとか生きのびていてくれたほうが、ずっとよかったのに。
不二聖心の図書館のアンネ・フランク展を契機として、生徒のみなさんのアンネ・フランクへの関心が高まっていることを感じます。ぜひ『思い出のアンネ・フランク』を読んでください。ミープ・ヒースという、「人間としての真実の美しさが映し出されている」人に出会ってください。祈るような思いでお薦めします。