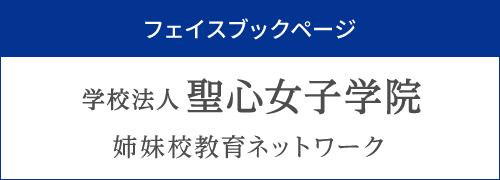フィールド日記

2013.02.14
蜂の巣に似ているハチノスタケ
2013.02.14 Thursday
第2牧草地の池の近くでハチノスタケを見つけました。管孔(キノコの傘の裏側に形成される器官)が蜂の巣状になっているところから、ハチノスタケと呼ばれます。
キノコの中には特定の樹木にだけ生えるものもありますが、ハチノスタケはさまざまな広葉樹に寄生することで知られています。特定の生物と結びつくことで繁栄をはかろうとする生き物もいれば、幅広くいろいろな生物と関わりを持つことで繁栄を勝ち得ようとする生き物もいます。自然界の生き物のつながりは実にさまざまです。


今日のことば
昨日の新聞から92 平成19年2月26日(月)
『物語の役割』(小川洋子 ちくまプリマー新書)を読む
―― 人間は、なぜ物語を必要とするのか? ――
2月18日の朝日新聞に、小川洋子の『物語の役割』という本についての、次のような短い書評が載りました。
小説家の空想力や想像力には、現実の中にちりばめられているたくさんの題材がヒントになる。誰もが現実を受け入れるために「物語」を紡ぎ出しているのだ。自作がイメージから言葉になっていく過程や、子ども時代の本の思い出などをテーマに、小川ワールドを語った講演録。(ちくまプリマー新書・714円)
この短い書評からもわかるように、小川洋子が問題にしている「物語」とは、「源氏物語」や「若草物語」といった文学作品だけを指すのではなく、広く現実の世界で生まれる「物語」をも含んでいます。書評には「誰もが現実を受け入れるために『物語』を紡ぎ出しているのだ」とありますが、そのようにして生まれた物語の例として、小川洋子は次のような話を紹介しています。
もう一人私がここで思い出すのは、1985年、日航ジャンボ機の墜落事故で、九歳の息子さんを亡くされたお母さんの姿です。私は遺族の方々が編まれた文集を読んだのですが、この九歳の坊やは生まれて初めての一人旅で、大阪のおじさんの家へ行く途中でした。当時人気のあった、清原、桑田のいるPL学園を応援するために、甲子園で野球観戦をする予定でした。それであの、JAL123便に乗ったのです。
たぶんお母さんは、スチュワーデスさんがいる分、新幹線より飛行機の方が安心だと思われたのでしょう。羽田まで息子さんを見送った別れ際、息子さんは「ママ一人で帰れる?」と言ったそうです。
なぜあの飛行機に乗せたのか。九年の人生で一番怖い思いをしただろう時に、どうしてそばにいてやれなかったのか。お母さんの文章は、始終自分を責める言葉で埋まっていました。直接そうは書かれていませんが、自分が子供を殺してしまった、という思いが伝わってきました。
恐らく同じ立場に立たされた母親なら、全員そう思うでしょう。一生自分を責め続け、自分を許さないでしょう。しかし、現実をありのままに見るなら、責任を取るべき人たちは他にいます。尾翼の不良を見逃した日航か、機体を製造したボーイング社か、同じ機体が以前しりもち事故を起こした時、調査した運輸省(当時)か……、とにかく責められるべき人がいるはずです。そして母親には何の落ち度もありません。
けれど、たとえそうした責任追及がきちんとなされ、原因がはっきり解明されたとしても、母親の罪悪感は消えないはずです。自分が子供を殺した、というフィクションの中に、苦しみの源を持ってくる。そういう苦しみ方をしなければ受け止めることのできない悲しみが、この世にはあるのでしょう。
事故からちょうど二十年が経った夏、テレビのニュースでそのお母さんの姿を拝見する機会がありました。遺族の集まりのリーダー的存在として、さまざまな活動を通し、空の安全を追求している様子が映し出されていました。もちろん、息子さんを失った悲しみは一かけらも消えていません。しかし、悲しみに押しつぶされるのではなく、それを礎として、自分の経験を社会のために生かそうと努力しておられる。そのお姿に胸を打たれました。
現実を棘で覆い、より苦しみに満ちた物語に変え、その棘で流した血の中から、新たな生き方を見出す。お会いしたこともないお母さんから、私は人間が作り出す物語の尊さについて教えられた気がしました。
ここに引用した物語は、日航ジャンボ機墜落事故が契機となって生まれた物語で、特殊な体験を綴ったものと言えるでしょう。このような体験をしていなければ、物語は生まれないものなのでしょうか。そうではないと小川洋子は考えます。『物語の役割』の中には、「物語はそこかしこにあるのです」や「誰でも生きている限り、かたわらに自ら作った物語を携えている」など、小川洋子の物語観がうかがわれる発言がたくさんあります。
「物語はそこかしこにある」という考えを説明するにあたって、小川洋子が取り上げたのは『ナショナル・ストーリー・プロジェクト』という本でした。『ナショナル・ストーリー・プロジェクト』は、アメリカの人気作家ポール・オースターが呼びかけて全米から集めた話を一冊の本にしたものです。ここでも一つだけ紹介しておきましょう。
ファミリー・クリスマス
(これは父から聞いた話だ。1920年代前半、私が生まれる前にシアトルであった出来事である。父は男六人、女一人の七人きょうだいの一番上で、きょうだいのうち何人かはすでに家を出ていた。)
家計は深刻な打撃を受けていた。父親の商売は破綻し、求職はほとんどゼロ、国中が不況だった。その年のクリスマス、わが家にツリーはあったがプレゼントはなかった。そんな余裕はとうていなかったのだ。クリスマスイブの晩、私たちはみんな落ち込んだ気分で寝床に入った。
信じられないことに、クリスマスの朝に起きてみると、ツリーの下にはプレゼントの山が積まれていた。朝ごはんのあいだ、私たちは何とか自分を抑えようとしつつ、記録的なスピードで食事を終えた。
それから、浮かれ騒ぎがはじまった。まず母が行った。期待に目を輝かせて取り囲む私たちの前で包みを開けると、それは何か月か前に母が「なくした」古いショールだった。父は柄の壊れた古い斧をもらった。妹には前に履いていた古いスリッパ。弟の一人にはつぎの当たった皺くちゃのズボン。私は帽子だったーーー 11月に食堂に忘れてきたと思っていた帽子である。
そうした古い、捨てられた品の一つひとつが、私たちにはまったくの驚きだった。そのうちに、みんなあんまりゲラゲラ笑うものだから、次の包みの紐をほどくこともろくにできない有様だった。でもいったいどこから来たのか、これら気前よき贈り物は? それは弟のモリスの仕業だった。何か月ものあいだ、なくなっても騒がれそうにない品をモリスはこつこつ隠していたのだ。そしてクリスマスイブに、みんなが寝てからプレゼントをこっそり包んで、ツリーの下に置いたのである。
この年のクリスマスを、わが家の最良のクリスマスのひとつとして私は記憶している。
ドン・グレーヴズ(アラスカ州アンカレッジ)
小川洋子は、「このなかに非常に深い物語が隠れている」と思うと言います。『物語の役割』は決して抽象的な物語論ではありません。このように深い意味を持った、いい話がたくさん紹介されていて、読んでいて飽きることがありません。とりわけ興味深く読んだのは、小学生の時に『ファーブル昆虫記』を通して小川洋子が学んだ、読書の意味についての話でした。続けて引用してみましょう。
小学校に入ってからの読書経験の中で、私を特に夢中にさせたのは、『ファーブル昆虫記』です。ご存知の方も多いと思いますが、その最初に取り上げられているのがスカラベ・サクレ、いわゆるフンを食べる虫、フンコロガシです。
牛や羊のフンを玉にして転がす習性があるこの虫は、体は丸くて平たく、黒光りしています。頭部のへりがシャベルのようになっていて、ギザギザの歯が付いており、前肢も同じくのこぎりの歯のようにギザギザしています。まずフンを見つけて飛んできますと、頭と前肢で適当な部分を切り分け、山の中からきれいに球形をくり貫きます。その途中で集ってきた他の仲間が多くて邪魔になると、前肢でパシンと叩き落としたりします。それから、くり貫いた球形の表面を、前肢の平たい部分をこてのように使ってつるつるに整えます。その時玉は地面の同じ場所に固定されたままで、雪だるまを作る時のようにクルクル回転させたりはしません。そして、完全な球形を作ってから初めて、他のスカラベに邪魔されない安全な巣穴まで運びます。それは自分の体よりもずっと大きな玉です。
この転がし方がユニークで、逆立ちをして後ろ向きに玉を押してゆくのです。二本の長い後肢で玉を抱えるようにして、その後肢の先にある爪を玉に刺して、そこを中心に回転させます。前肢で体重を支えながら、その前肢で地面を右左、右左と素早く押して、後ろ向きに進んでゆく。急な坂で失敗して転がり落ちても、でこぼこ道でも、十回でも二十回でも失敗しながら、がむしゃらに進みます。
途中、ずる賢いのがいて、やっと一つの玉を作り終え、さあ、と転がし始めたところに、お手伝いしましょうか、という風を装って親切そうに寄ってきます。本来の持ち主が、逆立ちをして一生懸命玉を押しているのを、お手伝いの方は、立ち上がった格好で引っ張るのですが、リズムが合わずに、とうとうお手伝いは手足を縮めて玉に張り付いて、玉と一緒に転がってゆきます。あとで自分がいただいてしまおうという魂胆のようです。あるいはそこで喧嘩になって、お互い玉の上と下ではたきあいになり、もうどっちが本来の持ち主か分からなくなって、とうとうはたき落とされた方が、最初から玉の作り直しをするはめになる、というような小さなドラマが繰り広げられます。
そうこうしながら、安全な気に入った場所まで玉を運ぶと、今度は食事用の穴を掘ります。だんだん穴が深くなってくると、心配になるのか、外に出るたびに玉の方をチラッと見て、「ちゃんとあるな」と確かめます。それでもまだ安心できない時は、玉に触ってみたりもします。それで元気を取り戻し、また巣穴を掘りはじめます。そこへ食料となる玉を入れ、自分も中に入り、土で入り口を塞ぐ。あとはゆっくり食べるだけです。
私は、広々とした草原で、懸命に玉を転がしてゆくスカラベの姿に思いを馳せました。彼らは道具等一切使わず、神様から与えられた、生まれ持った自分の体だけを使って、完全なる球形を作り出します。誰に教わるのでもなく、練習してそうできるのでもなく、生まれながらにして玉つくりの名人なのです。ファーブルはスカラベのことを、「天才だ」と書いています。
さて、このようにして小川洋子はスカラベの話を紹介しているのですが、この話を読んで最も強く心に残ることは何でしょうか。フンを転がすというスカラベの生態のユニークさでしょうか、フン玉の取り合いの激しさでしょうか、その持ち主が簡単に入れ替わってしまうことの理不尽さでしょうか。さまざまな点で興味深い話ではありますが、『博士の愛した数式』の作者は、たいへん独特な読み方をしています。続けて引用してみましょう。
自分が立っているのと同じ地続きのこの地面の向こうで、自分とは全く異なる姿かたちをした生き物が、自分とは全く違う方法で生きている。遠すぎて見えない場所にもちゃんと世界があって、そこも神様の見事な計らいによって守られている。私は『ファーブル昆虫記』を読んで、何とも果てしない気持ちになりました。自分が何か偉大で巨大な全体の一部分であり、その部分をスカラベと平等に分け合っている、という気持ちとも言えるでしょうか。自分というささやかな存在に振り回されるのではなく、そこから一歩離れて、世界を形作っている大きな流れに身を任せることの安心感を、『ファーブル昆虫記』によって私は味わったのです。
小川洋子の考える「物語の役割」の一つがここにあります。つまり、私たちは、物語を読むことを通して「何か偉大で巨大な全体」に触れ、「自分というささやかな存在に振り回されるのではなく、そこから一歩離れて、世界を形作っている大きな流れに身を任せることの安心感」を味わうことができるというのです。
平成18年度の「昨日の新聞から」は92号で終わりとなります。64号(『藍の空、雪の島』を読む)のカンボジア難民の話から92号のスカラベの話まで、実に多くの物語を紹介してきましたが、良い物語というものは確かに自分という小さな存在を離れて大きな世界へと私たちを誘い、「大きな流れに身を任せることの安心感」を感じさせてくれるものだと強く思います。
新しい年度においても、「大きな流れ」の存在に目を開かせてくれる、すばらしい物語との出会いがあることを祈りつつ、今年度の「昨日の新聞から」を終わりにしたいと思います。