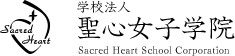シスター・先生から(宗教朝礼)
2025.11.05
2025年11月5日放送の宗教朝礼から
先日の秋のつどいでは、多くの人に充実したひとときを与えてくださり、ありがとうございます。発表系クラブの仲間と目を合わせる姿や、呼吸がそろった時の一体感。運動系クラブの出し物で、丁寧に対応しながらたくさんの笑顔を生み出していた姿。そして、これまでの準備の過程が伝わってくる、工夫を凝らした展示など、それらすべてにおいて、ただ見せるだけでなく、何かを伝えようとする皆さんの思いが感じられ、深く感動しました。皆さんの姿から、気づかされ、学ばされることが多くあるのだと、改めて実感した一日でした。今回のように皆さんの内面性が、見事に発揮されたこの夏の出来事を今日は分かち合いたいと思います。
日本の最高峰である富士山に見守られ、私たちは生活しています。富士山を見て嬉しくなったり、心がほっとしたり・・、知らず知らずのうちに富士山の存在が私たちの心の拠り所になっています。この環境で過ごせることは、本当に贅沢で、恵まれていることだと感じます。不二聖心では3年に1度、高校生対象に富士登山が行われています。コロナの影響で中断していましたが、この夏、2018年度以来、7年ぶりに富士登山を実施することができ、私も引率として登ってきました。普段は優しく私たちを見守り、美しい姿の富士山ですが、登山となるとその印象は一変し、自分との戦いが始まります。ひたすら続く登り坂、だんだん空気も薄くなり、人によっては高山病で頭痛や吐き気も出てきます。さらに、山の上ではすべてのものが貴重で、水さえ自由には使えません。手を洗うことも、水道から水を飲むこともできません。トイレも少なく、有料で、水洗式ではありません。数少ない山小屋の売店では500mLの水が500円前後するほど何もかも高いのです。山頂でご来光を見るために、私たちは8合目の山小屋で夕食と仮眠をとりました。夕食のカレーは、量は多くなく、お茶もコップ半分ほど。当然おかわりはありません。一口一口を心からありがたくいただき、今まで食べたカレーの中で一番おいしいね!と皆で話しながらいただきました。もちろんシャワーはありません。登山で汚れた服装のまま、硬い木の棚のような場所で生徒も教員も一緒に横になります。気温は、7℃程でとても寒かったです。でも、暖房はなく、あるのは寝袋1枚。疲れているのにぐっすり寝ることはできないし、電気もほんの小さな豆電球のみ。まるで、何十年も前の生活のようでした。でも、不二聖心の生徒から不満やわがままを言う声はまったく聞こえてきませんでした。
この苦しく不自由な環境こそが、私たちに大切な気付きを与えてくれました。まず、「当たり前」がいかにありがたいか、ということです。水、トイレ、布団、屋根など、日本に住む私たちにとって当たり前にあるものは、生きていくために必要で、大切に使わせてもらわなければいけないということに改めて気づかされました。また、過酷な環境のなか、「大丈夫?」という友達の声掛けや、すれ違う人の「あと少しだよ、頑張れ」という挨拶。その何気ない一言が、本当に支えになりました。皆で歯を食いしばり、励ましあいながら、登る先には、刻々と変わる景色が待っていました。澄み切った空気、手が届きそうなほどの星の美しさ、太陽の光の温かさ、そして空の青さ。普段は当たり前すぎて、何も感じないことが、苦しさを乗り越えた先だからこそ味わえる、最高の景色と達成感になりました。
不二聖心の生徒たちは、苦しい中でも誰一人として弱音を吐きませんでした。それどころか、学年を超えて互いに声を掛け合い、体調を気遣う配慮がありました。寒そうにしている子に自分の上着を差し出す生徒。苦しそうにする子に携帯酸素を差し出す生徒。足取りが重い子の荷物を持ってあげる生徒。あちらこちらで「ありがとう」という言葉も聞こえました。
マルコによる福音書やルカによる福音書に「やもめの献金」のお話が記されています。イエスは、金持ちたちが献金をするのに対し、貧しいやもめが、なけなしのお金であるレプトン銅貨二枚を捧げた姿を見て、こう言われました。
「この貧しいやもめは、賽銭箱に入れている人の中で、だれよりもたくさん入れた。皆は、有り余る中から入れたが、
この人は、乏しい中から、自分の持っている物をすべて、生活費を全部入れたからである。」
(マルコによる福音書12章41~44節、ルカによる福音書21章1~4節)
自分が豊かなときや余裕があるときに人に「どうぞ」と気遣うこと。それは素晴らしいことです。しかし、自分自身も同じように苦しく、乏しいなかで相手を思いやり、「どうぞ」と差し出せること。これこそが本当に尊い行いだと思います。不二聖心の生徒は、日頃からありがたさを感じられる心を持っています。だからこそ、極限の状況でも、自然と他者を思いやる気遣いができたのだと感じます。生徒たちが見せてくれた姿は、イエスが最も尊いと称賛したやもめの姿と重なるものでした。
便利なもので溢れている現代に、私たちは生きています。この富士山の環境も、今の時代、もっと便利にしようと思えばできるのかもしれません。でも、私は富士山はこのままがいいと強く思います。昔からこの形が守られ続けてきたことには意味があり、この環境こそが、私たちを大きく成長させてくれるのです。苦しさがあるからこそ、本当の成長があり、自分の欲を抑え、我慢することの大切さを、富士山は改めて教えてくれました。これは、私たちが日頃大切にしているWorld Smiles Lunchや、12月から始まるプラクティス、クリスマスチャリティセールの精神にも通じます。単に寄付をするだけでなく、少し我慢し、その思いを他者と共にする。そして、相手を笑顔にする。これこそが聖心の生徒のあるべき姿です。
引率として、富士登山の危険性も十分に感じていましたし、久しぶりの実施ということもあり、不安な気持ちも大きかったのも事実です。だからこそ、生徒の姿、行いに本当に力をもらいましたし、心から感動しました。今回のメンバーが特別ではなく、「不二聖心の生徒たちなら、誰を連れて行っても、このように行動できる」と自信をもって言えます。雄大な富士山に見守られながら、皆さんがこれほど豊かに育ってくれていること、そのような教育に携わることができていることを、心から嬉しく、そして誇りに思っています。
Y.O.(保健体育科)