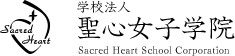シスター・先生から(宗教朝礼)
2025.09.24
2025年9月24日放送の宗教朝礼から
これから宗教朝礼を始めます。
最近の楽しみの一つにオートバイの修理があります。今年、これまで乗っていたバイクを売って、新しくホンダの小型バイクをネットオークションで買いました。そのオートバイは40年以上前に製造されたモデルで、商品の説明欄によると、この20年ほどは倉庫で放置されていて、今では動かないということでした。動くバイクを売って、壊れたバイクを買うというとちょっと意味が分からないかもしれませんが、もともと壊れたものを修理するのが好きで、いつかバイクも直してみたいと思っていたので、今年挑戦することにしました。ただ、実際に届いたものを見ると、思っていた以上に劣化していて、ちょっと無理かもしれないと気後れしたのを覚えています。それでも、Youtubeなどで勉強しながら、ブレーキをばらして磨いたり、タイヤを外してベアリングを交換したりなど、1つ1つ直していくと、少しずつ形になっていきました。そして、肝心のエンジンですが、キャブレターというガソリンと空気を混ぜるパーツを綺麗にし、スイッチを押すと、トコトコと小気味良い音を立てながら動き出しました。40年前に作られて、20年も放置されたエンジンが、今でもちゃんと動くということに感動し、こうしたものづくりにどのような思いが込められているのか興味がわき、ホンダの創業者である本田宗一郎氏について調べてみることにしました。宗一郎氏は1906年に現在の浜松市天竜区の村で、鍛冶屋の長男として生まれました。小さいころから機械に興味を持ち、初めて見た自動車に魅せられて、その後16歳で単身上京し、自動車修理工場で働き始めます。自動車の修理工として順調に働いていましたが、関東大震災によって工場が全焼してしまいます。それでも、宗一郎氏は苦難の中で工場再建に貢献し、その技術を認められて22歳で独立、浜松に自動車修理工場を開業します。修理工場は評判も良く順調でした。しかし、宗一郎氏はただ人の作ったものを修理するのではなく、自らの手でものを生み出したいと、周囲の大反対にあいながらも、ピストンリングというエンジンの重要な部品をつくる会社を立ち上げます。しかし、ピストンリングの開発は失敗続きで、会社はたちまち倒産の危機に陥ってしまいます。知識不足を痛感した宗一郎氏は30歳にして現在の静岡大学工学部の夜間部へ入学し、熱心に研究をしました。そうして破産寸前のところで、ついにピストンリングの開発に成功し、会社は軌道に乗りました。しかし、また苦難が訪れます。太平洋戦争によって浜松の町は焼け野原となり、再びすべてを失ってしまったのです。そのような中でも、宗一郎氏は諦めませんでした。戦後の大変な中で人々の移動を少しでも楽にしてあげたいと、旧陸軍の無線機用の小型のエンジンを自転車に取り付けるアイデアを思いつきます。これがとても評判となり、続けてオリジナルのエンジンの開発も始めます。これがホンダのオートバイメーカーとしての始まりでした。その後、レースで世界一となるという夢に向けて開発を進め、世界のホンダとして発展していくことになります。こうしてみると、決して順風満帆な成功物語ではなく、いくつもの苦難にあい、失敗を重ねながらも、決してあきらめることなく、人の役に立ちたいと挑戦を続けた結果の成功であることが分かります。宗一郎氏は母校の小学校の創立100周年を記念し、次の言葉を贈りました。
「古くからの言い伝えに、『見たり、聞いたり、試したり』という言葉があるが、私は、この中で一番大切なことは試してみることだと思います。最近のようにラジオ、テレビなどが発達していると、見たり、聞いたりすることは非常に多いが、実際に試してみる人は少ないように思われます。ことに実行には失敗はつきものです。失敗したらなんで失敗したか、その原因をよく確かめること、つまり反省してみることが大切です。ふたたび同じ原因の失敗を繰り返すようでは、正しい反省をしていない証拠であり、 また成功に通ずることもありません。皆さんは失敗をおそれず、勇気を出して試してみる人になってください。」
これは今から50年前に贈られた言葉ですが、SNSやAIが発達し、簡単に答えや結果が調べられてしまう現代こそ、実際にやってみる経験やそこから学ぶことの重要性がより高まっているように思います。不二聖心では先日発表されたイタリアのスピンオフ企業であるVISとの連携をはじめ、様々なサイエンスやテクノロジーに関連した大学や企業との連携が進んでいます。皆さんの中にも理科系の進路を目指そうと考えている方がますます増えていると感じます。理科の教員として大変うれしいことです。前教皇フランシスコが書かれた『ラウダート・シ』の中で、テクノロジーについて述べられている部分があります。その中で、教皇フランシスコはテクノロジーがもたらす恩恵を認め、科学者やエンジニアに謝意を示す一方で、無条件に科学を信奉し、すべてを解決できると過信することへの警鐘を鳴らしています。科学に支配されるのではなく、私たち人間が何が正しいかをしっかりと見極め、正しく用いていくことを求められています。理科の教員として、カトリック学校である不二聖心で学ばれた皆さんが、サイエンスやテクノロジーの世界で、真に価値あるものを見分けられる人として活躍されることを願っています。
これで宗教朝礼を終わります。
参考文献
那須田 稔 (1985).『空とぶオートバイ: 本田宗一郎物語 (ひくまのノンフィクション 4)』ひくまの出版.
教皇フランシスコ (2015).回勅『ラウダート・シ――ともに暮らす家を大切に』カトリック中央協議会.
M.H.(理科)