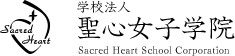シスター・先生から(宗教朝礼)
2025.09.03
2025年9月3日放送の宗教朝礼より
今日は夏休み中にあった、ある本との出会いをお話ししようと思います。
7月の最後の日曜日、私は夫と小さな本屋に出かけました。今でも暑い日が毎日続きますが、その日もとても暑い日で、私たちはお店に入るなり「涼しっ!」と声に出してしまい、店主さんの視線を浴びてちょっと恥ずかしかったのです。その視線を避けたくて、私は店の真ん中にあるテーブルに平置きされた本に目を向けました。すると、とてつもなくビビットな表紙でとても目立つ本が目に飛び込んできました。店主さんが私の方を見ている気配は既にありませんでしたが、あまりにもショッキングな色合いの表紙に私の眼はくぎ付けになり、気が付いたらもうその本を手にしていました。表紙では女の子が片足を高くあげています。でもその足が右足なのか、左足なのかはっきりしません。顔の向きと体の向きがちぐはぐなのです。言ってしまえば子どもが描くような絵です。でもだからといって下手くそな絵かというと、そうでもありません。上手だとか下手だとか、そういうことではない。とにかく個性的な絵なのです。「横顔がなんとなく古代エジプトの壁画とかに似ているのかな」とも思いましたが、自由で躍動感にあふれている女の子の姿からは、壁画にあるような堅苦しさは感じられません。単純な線で描かれたマンガのような、落書きのような絵なので、写実的ではありません。でも今まさに踊っているようなリアルさがある、とても不思議な魅力をこの絵に感じたのです。私はこの本に完全に引き込まれてしまいました。
本の帯には「作 サンギータ・ヨギ」とあります。聞いたこともない名前です。翻訳は小林エリカとあって、こちらはプラン・インターナショナルの「わたしに違う人生があることすら知らなかった。」という女の子の広告で馴染みのある名前です。頭に浮かんだ小林エリカさんの描いた絵とこの表紙の絵は全然タイプが異なるので、ちょっと違和感を感じます。でも、女の子を支援するCMに協力したり、風船爆弾をつくった女の子たちのことを小説にした小林さんが訳したということは、この本のテーマがなんとなく想像できます。女子校勤めの私としては、中身がますます気になってきました。(それに、風船爆弾の本は最近読んだばっかりだったので、この本との出会いがますます運命的に感じられて
きました。)はやる気持ちを抑えつつ表紙をめくると、私はもうその蛍光色の世界に取り囲まれてしまいました。この本はどのページもポップで、どのページにも女性が描かれているのです。アクロバティックな格好をした女、座って花飾りを作る女、着飾った女、ダンスする女、歌う女、街中の女、船に乗る女、子どもたちに教える女、女、女、女!かわいい女たちの中をよくよく探すとたまに男。この本のタイトルは「わたしはなれる」。思った通り、その「わたし」は女性のことだったのです。
気が付くと、夫もこの本をのぞき込んでいます。夫はまあまあの本好きなので、「ねえこの本、どう思う?」と夫に本を渡すと開口一番「すごい色だなあ。でも西加奈子が推薦してるんだね。」帯には「女の子であること、それだけで強いんだ」という推薦文が書いてありました。そして裏表紙を見て「こんなおばさんが書いた本にしては高いな」というのです。私も値段を見てみると、消費税を入れると約4000円です。確かにちょっとお高いかも。そんなやりとりを見ていた店主さんが私たちに近づいて来ました。
その高い本『わたしは なれる』は、店主さんの話によると、日本語版といっても日本で印刷されたものではなく、世界一美しい本を作ると言われている、インドのタラブックスという会社によってインドで印刷されたもので、それを日本に輸入して売っているのだそうです。値段が高いのはそれが理由なのかもしれません。作者のサンギータはインド北部に生まれた25歳の女性で、小学2年生までは学校に通うことができたけれど、働くことを強いられ、幼くして大家族に嫁ぎ、一男三女の母になったのだそうです。兄たちの家族と同居する男性を夫としたため、嫁ぎ先では家事を一手に担わなければならず、義理の兄たちの子供の面倒もみなければならない、そんな境遇にこのサンギータはおかれたのでした。「そうか、この作者は25歳にして既にベテランのお母さんなのか…。」夫が写真を見て、実年齢よりも年上にこの女性を見てしまったのは、そのお母さん感のせいかもしれません。その若いお母さんは、この本でどんなことを語ったのだろう。私はもうこの本を買って、じっくり読むしかないと思っていました。
さて、ここまで紹介してきたのですから、みなさんはきっとこの本のあらすじをこれから聞けると思っていることでしょう。でも残念ながら、私は今日この本の内容を語りません。なぜなら夫がこんなことを言ったからです。「この本って文章は全部編集者が書いたんだね。作者がインドの公用語を読み書きできないから、聞き書きによって作られたって書かれてる。だから作者は出来上がった自分の本を読むことができない。で、僕たちが読んでいる日本語の文章は、おそらく英語から翻訳されている。作者は自分の本が読めないし、僕らは作者の言葉に直接触れることができない。とてつもない言葉の壁だよ。でもさ、絵は作者自身のもの。絵があることで作者と直接コミュニケーションをとれる。絵本っていいよね!」ということで、私は言葉でこの本を紹介するのはちょっと違うのかな、と思ってしまったのです。ですので、みなさんぜひこの本を手に取って、見てみてください。本屋さんでの立ち見でも十分そのメッセージを感じることができます。図書館ならもっとゆっくり眺められるでしょう。もちろん買うのが一番。作者サンギータの収入になるからです。今日私があらすじを語らないのは、私の拙い言葉でこの本の魅力をうまく表現できる自信がないからでも、紹介文を書くのがめんどくさくなったからでもありません。ましてや、私にとってこの夏休み一番の出会いを独り占めしたくなったから…、なんてことはけっしてありません!ですので、やっぱり一言オススメすることにします。
みなさんは自分の好きなことを現実のせいにしてあきらめたりしていませんか?自分の未来は自分にしか作れません。思うようにいかないからって、前に進むことをやめてしまったらそれまで。どんな逆境にあっても、自分の未来は自分で切り開けるはず。学校にも満足に通えなかった、女性の権利が蔑ろにされる現実の中でも、好きなことを決してあきらめなかった女性の描いた絵本です。「好き」がもつエネルギーをその目で感じてください!
最後に。もうすぐ祈りの会、家で聖書の用意をしながらふと思いました。新訳聖書は約2000年前のイエスの言葉を、弟子たちが書き残したものです。旧約はもっと前。そんな古い聞き書きをさらに日本語に訳しているのですから、そこにはとてつもない言葉の壁があることになります。でも私は言葉の壁を感じたことはありません。聖書は絵本ではないのに、なぜなのでしょう?祈りの会でその答えに近づけるかしら?とちょっと楽しみな気持ちになりました。みなさんも祈りの会で何か1つ自分なりの問いを見つけ、その答えを探してみてください。
M.S.(技術・家庭科)