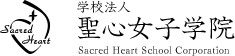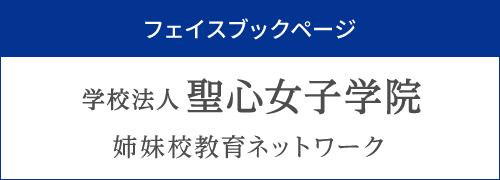不二聖心からのお知らせ

2022.05.11
2022年5月11日放送の宗教朝礼から
おはようございます。これから宗教朝礼を始めます。
5月になり、新緑の季節を迎えました。花粉症のシーズンが終わり、梅雨の湿り気がやってくる前のこの時期が、私は一番好きな季節です。木々の芽吹きや若葉の鮮やかな緑は、私に大きなエネルギーを分けてくれます。日本から8000km以上離れたウクライナでも、この5月は特に過ごしやすい時期で、大陸性の厳しい寒さとなる長い冬を乗り越え、雪融けの春を過ぎた今頃は、ライラックやアカシアの花が美しく咲き、例年であれば多くの観光客が訪れる観光のハイシーズンとなります。しかし、残念ながら今この瞬間もロシアによるウクライナ侵攻が続いています。大切な家族、友人、地域の隣人、そして自分自身の、命や人生、故郷を戦争によって奪われたウクライナの人々の苦境を思うと、言葉が出てきません。
2月24日以後、私はある作家の作品を時間を見つけては再読するようになりました。ウクライナ、ベラルーシ、ロシアにルーツを持つ作家、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチです。彼女はかつてのソ連で起きた戦争や原発事故、連邦崩壊の苦難に見舞われた「小さき人々」の声、いわゆる英雄や有名人ではない、私たちと同じ名もなき市井の人々の何百・何千という声を丹念に掘り起こし、記録してきました。彼女の作品は「苦悩と勇気の記念碑」と評価され、2015年にノーベル文学賞を受賞しています。彼女の著作の1つに、『ボタン穴から見た戦争』という作品があります。漫画化もされた代表作『戦争は女の顔をしていない』と同じく、第二次世界大戦期の独ソ戦を取り上げています。『戦争は女の顔をしていない』は女性の視点から見た戦争の剥き出しの姿を描き出した作品ですが、『ボタン穴から見た戦争』は当時小さな子どもであった101人の過酷な経験の告白を通じて、埋もれていた戦争の姿を炙り出した作品です。そのうちの一部だけ、紹介します。これは、ファイナ・リュッコという当時15歳の女の子のお話です。
(中略)みんな黒かった、真っ黒だった……奴らは犬まで黒かった……
私たちはお母さんたちにぎゅっと身を寄せていた。奴らは全員を殺したわけじゃないの、村のみんなを殺したんじゃないんです。右に立っていた人たちを捕まえたんです。それから子供と親は別々に並ばせた。あたしたちは、親は銃殺になって、あたしたちは残されるんだと思った。大人の中にお母さんがいました。私はお母さんなしで生きていきたくなかったので、大人たちのほうに行かせてくれとせがんで泣きました。お母さんはそれを見て叫んだんです。「これはあたしの娘じゃないよ!」って……
「おかあちゃん!」
「あたしの娘じゃないよ!あたしの娘じゃないよ……」
忘れられません。お母さんの眼は涙じゃなくて、血ばしっていた。目一杯血ばしっていて「これはあたしの娘じゃないよ」って。
(岩波現代文庫『ボタン穴から見た戦争』p134-p135)
ウクライナの多くの子供たち、多くの「小さき人々」の日々が戦争の一色で塗りつぶされている今、同じく「小さき人々」の私たちにできることはなんでしょうか。するべきこと、気をつけるべきことはなんでしょうか。
コラムニストの師岡カリーマ・エルサムニーは、ウクライナの人々の悲劇に対して最大限の同情と憤りを示し、ロシアによる侵攻を極めて強く非難した上で、次のように述べました。
「誰が加害者で、誰が被害者か、白黒のつけやすさゆえに、世界の人々は自ら考えるという労を要さない安易な勧善懲悪の悦に浸りすぎてはいないか(p9)」
「これほど簡単に正しい側につける紛争はめずらしい。それをいいことに、メディアも政治も私たち市民も、考えることを放棄していないか(p10)」
(岩波書店『世界』臨時増刊号「ウクライナ侵略戦争ー世界秩序の危機」)
と。
ライターのブレイディみかこは、詩人の谷川俊太郎との往復書簡において、アレクシエーヴィチの作品に触れつつ、次のように語りました。
どこを切っても金太郎飴のように天使の顔しか出てこない人間もいなければ、悪魔の顔しか出てこない人間もいない。(中略)
それなのに、どこかで戦争がはじまると、わたしたちは金太郎飴の思考に傾きがちです。(中略)でも、それではまた偉大な物語や英雄の話に逆戻りして、「小さき人々」が見えなくなってしまう。私は谷川さんからいただいた詩を思い出しました。
道端の萎れた花束に目を留めて
それをコトバにしようとするけれど
人の役に立たないそのミクロな行動は
地球上の人類が直面している困難と
なんの関わりもない
と 彼は考える
きっと人間たちは、巨大な危機に直面しているときこそ、道端に捨ててある花束に目を留めなければならないのです。道端に花束を捨てた人の気持ちや、ゴミ箱の中の花束に自分を重ねる人のことを、言葉にしなければならない。大きな言葉の劇的な洪水にさらわれ、自分では考えてもいなかった場所に流されてしまわないように。
(岩波書店『図書』2022年5月号,p40)
私は高校2年生の地理特講の授業で、社会問題に関する文章を読んでのディスカッションを行なっています。今年は私自身を含めて10名の「小さき人々」しかいませんが、10名の中で一つとして全く同じ意見、というものはありません。同じ賛成・反対でも、一人ひとり着目する場所が違っています。授業が進むにつれて、それぞれの意見は紛糾し、収束するどころかますます多様性があらわになってきます。もしこれが、何かしらの偉大な物語や英雄の話に収めようとそれぞれが配慮したり、沈黙したり、わかりやすいストーリーになんの疑問も持たずに乗っかってしまったりしたら、議論が成り立ちませんし、何の変化や反応も起こりません。ですが、日常生活や社会に目を向けると、そうした事象はいくらでも見られます。アレクシエーヴィチは偉大な物語を神話と言いかえ、こう話しました。
『神話の麻酔は恐ろしいものです。政治家だけではありません。「小さき人々」も神話というものが好きなのです。「小さき人々」は、誰よりもこの神話というものに苦しめられているにもかかわらず、この神話と別れるのがとてもつらいのです』
(岩波書店『アレクシエーヴィチとの対話 「小さき人々」の声を求めて』p134)
と。偉大な物語やわかりやすい物語のおさまりのよさに安住し、「小さき人々」の一人ひとりの声の存在を忘れてはいけませんし、皆さん自身が、この「小さき人々」の一人として、自ら考え、沈黙に抵抗し、責任を持って自分の言葉を、自分の祈りを発していかなくてはいけません。
大きな武力を前に、言葉の頼りなさを感じることがあるかもしれません。評論家の加藤周一はかつて次のように述べました。
「言葉は、どれほど鋭くても、またどれほど多くの人々の声となっても、一台の戦車さえ破壊することができない。戦車は、すべての声を沈黙させることができるし、街(原文=プラハの)全体を破壊することさえもできる。しかし、(プラハ)街頭における戦車の存在そのものをみずから正当化することだけはできないだろう。自分自身を正当化するためには、どうしても言葉を必要とする。すなわち相手を沈黙させるのではなく、反駁しなければならない。言葉に対するに言葉をもってしなければならない。」
(ちくま学芸文庫『言葉と戦車を見すえて』p233)
このような時だからこそ、私たちは平和を求める声を上げていかなくてはならないのではないでしょうか。言葉を積み重ね、分かちあいを重ねていくことでしか、世界を平和のうちに変えていくことはできないと、私は考えます。
最後に、教皇フランシスコの今年の復活祭のメッセージの一部を唱えます。
残酷で無意味な戦争に引きずり込まれ、暴力と破壊によって傷めつけられたウクライナに、平和が訪れますように。この苦しみと死の恐ろしい夜に、新しい希望の夜明けが早く訪れますように。平和のための決断がなされますように。人々が苦しんでいるときに、力で威嚇するようなことはやめましょう。どうか、戦争に慣れてしまわないでください。平和を希求することに積極的に関わりましょう。バルコニーから、街角から、平和を叫びましょう。「平和を!」と。
(https://www.cbcj.catholic.jp/2022/04/18/24537/から抜粋)
これで、宗教朝礼を終わります。
S.N.(地歴公民・社会科)